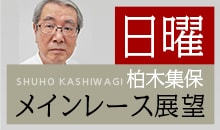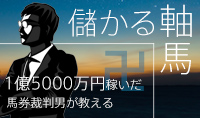天皇賞・春
- 2012年04月30日(月) 18時00分
- 128
レースのあと、注目のオルフェーヴルのあまりのレース内容に「むなしく、残念な空気」ばかりが流れた。しかし、そのことは置いて、例によってGIの週に多い異常な高速の芝に転じたコンディションを考慮しても、伏兵ビートブラック(父ミスキャスト)の歴代2位となる3分13秒8の圧勝劇は賞賛しなくてはならない。レコードと0秒4差である。
おそらく最初は控えるだろうオルフェーヴルを中心に、人気上位馬は差しタイプ。高速馬場が判明するにつれ先行馬の再チェックが行われたが、ビートブラックは前回の阪神大賞典3000mは大失速して4秒0差の大敗(10着)。そのビートブラックの果敢な先行策と、ましてやそのまま押し切って4馬身差の独走があるなど想像を超えていた。単勝15,960円は納得。しかし、それでも3連単は1,452,520円にとどまったから、3連単ファンの買い方はうまい。
石橋脩騎手の勝利コメントにも再三出たように「行かなければレースにならない」と思える高速の芝。好スタートのビートブラックは最初、あくまで先手を主張したゴールデンハインドの2番手に下げたが、2周目の3コーナーから早くも自力で強気なロングスパートをかけた。レース全体の流れは、800mごとに分けると、47.6-48.9-49.4-47.秒=1分36秒5-1分37秒3。
前後半の1600mにたった0.8秒の開きしかない完ぺきなまでの一定ペースで、最初の1ハロンを別にするとハロン13秒台は一度もないから見事だった(奇しくも昨秋の菊花賞と同じ)。なおかつ、3200m3分13秒8は、ビートブラック(石橋脩騎手)がほぼ自力で記録したタイムである。
2006年、それまでの天皇賞・春のレコードを大幅に短縮したディープインパクトの3分13秒4のレース中身は、次のようだった。
48秒1-49秒6-50秒9-44秒8=1分37秒7-1分35秒7
ディープインパクトの3コーナーからの強烈なロングスパートと、最後の4ハロンをすべて11秒台でまとめての上がり3ハロン33.5秒はまさに驚異。規格外に近いが、タイプの異なるビートブラックは前半からペースを落とすことなくほぼ一定のペースで先行し、かつ3コーナーでゴールデンハインドを交わして11秒台にピッチをあげた。ここの決断が素晴らしい。それでそのまま押し切ってみせたから、こと3200mの記録とするとディープインパクトの日本レコードとさして違わない価値を認めたい。
2着に追いあげたトーセンジョーダン、3着に伸びてきたウインバリアシオンは、前半の1600m通過地点で先行のビートブラックから少なくとも20~25馬身あったから、推定1分40秒0近い前半の通過か。離して飛ばした先行馬のいなかった2006年のディープインパクト自身の前半1600m通過も、だいたい1分40秒0前後だった。推測なのでもちろん誤差はある。
したがって、トーセンジョーダン(岩田康誠騎手)、さらにそのあとにいたウインバリアシオン(武豊騎手)は、まさかビートブラックがそのままのペースを保って粘り込むとは思いもよらなかったが(ファンとも同じ)、2頭はディープインパクトではないから、あのペースで前半の1600mを通過した時点で、3分13秒台で乗り切ることは不可能である。
ビートブラックに4馬身、さらに2馬身の差をつけられての完敗は、対ビートブラックではなく、同じ位置にいて一気に進出して行ったディープインパクトを仮想の勝ち馬とすると分かりやすい。ディープインパクトのように3200mで上がり44秒台(推定5ハロン56秒台)など、それは不可能。だから、あの位置にいた時点で、どういう差し追い込み馬もディープインパクトのように3分13秒台は無理となった。
ところが、先行したビートブラックはまったく逆の戦い方で、芝状態を読み、レース前にはとても無理だろうと思えた高速の3200mを乗り切ってみせたのである。石橋脩騎手は、ふだん夢中になるとあまりにも鞭を連打しすぎるとされるが、この天皇賞・春のペース感覚と、スパート判断は、決して「イチかバチか」ではない。歴史的な好騎乗である。
長距離重賞で、評価の低い伏兵先行馬の逃げ込みを許したときの、人気の差し=追い込み馬の騎手の心情はつらい。つまるところ「ペース判断ができなかった。的確ではなかった」ということになるが、今回はビートブラック(石橋脩騎手)があまりに素晴らしすぎたから、仕方がない面もあるだろう。ただし、負けた人気上位馬の上がりは3200mのGIなのにまだみんな脚があった「33秒台~34秒0」である。どうみても前半あまりにタメ過ぎていたことは否定できない。
多くの人びとに、「いったいどうしたのだろう」。あまりにも残念なレースの印象を残し、むなしいチャンピオンを感じさせたオルフェーヴルは、すっかり人間不信に陥った悲しい馬のように映った。今度は「大丈夫」と思わせる動きをみせ、体つきも決して悪くはなかったが、それは天才オルフェーヴル(4冠馬)の虚勢だったかもしれない。パドックも悪くはなかった。でも、威厳とオ-ラがなかった。
阪神大賞典。自身が気負い過ぎたことは確かだが、再三再四、どう考えてもレースを止めるように指示されたのが信頼する池添謙一騎手であり、なんとか止めたら、また走れという。あのあとの中間、あまり好きでもないEコースで、みんなが息を詰めるように見つめる中で、調教再審査といういわれのない走法審査。みんなの自分を見つめる目が以前とはちがっている。信頼し、一番気心の知れているはずの人たちが「危険な馬」を見るように距離を置いている気がする。疲れとか、筋肉の動きとか、脚元がどうのとかではなく、「こころ」の動きを含めた体調が落ちていたとしか思えない。
自身満々に破格の3分02秒8で好位から抜け出した菊花賞3000mと同じような距離なのに、闘志に点火し、スパートを開始しなければならない勝負どころの2000m地点は、あの日より約「2秒」も遅い通過である。みんなはもっと先に行っている。オルフェーヴルは走っていて悲しかった。4コーナーで大きく外に回りかけたときには、もう明らかにオルフェーヴル自身があきらめていた。
おそらく最初は控えるだろうオルフェーヴルを中心に、人気上位馬は差しタイプ。高速馬場が判明するにつれ先行馬の再チェックが行われたが、ビートブラックは前回の阪神大賞典3000mは大失速して4秒0差の大敗(10着)。そのビートブラックの果敢な先行策と、ましてやそのまま押し切って4馬身差の独走があるなど想像を超えていた。単勝15,960円は納得。しかし、それでも3連単は1,452,520円にとどまったから、3連単ファンの買い方はうまい。
石橋脩騎手の勝利コメントにも再三出たように「行かなければレースにならない」と思える高速の芝。好スタートのビートブラックは最初、あくまで先手を主張したゴールデンハインドの2番手に下げたが、2周目の3コーナーから早くも自力で強気なロングスパートをかけた。レース全体の流れは、800mごとに分けると、47.6-48.9-49.4-47.秒=1分36秒5-1分37秒3。
前後半の1600mにたった0.8秒の開きしかない完ぺきなまでの一定ペースで、最初の1ハロンを別にするとハロン13秒台は一度もないから見事だった(奇しくも昨秋の菊花賞と同じ)。なおかつ、3200m3分13秒8は、ビートブラック(石橋脩騎手)がほぼ自力で記録したタイムである。
2006年、それまでの天皇賞・春のレコードを大幅に短縮したディープインパクトの3分13秒4のレース中身は、次のようだった。
48秒1-49秒6-50秒9-44秒8=1分37秒7-1分35秒7
ディープインパクトの3コーナーからの強烈なロングスパートと、最後の4ハロンをすべて11秒台でまとめての上がり3ハロン33.5秒はまさに驚異。規格外に近いが、タイプの異なるビートブラックは前半からペースを落とすことなくほぼ一定のペースで先行し、かつ3コーナーでゴールデンハインドを交わして11秒台にピッチをあげた。ここの決断が素晴らしい。それでそのまま押し切ってみせたから、こと3200mの記録とするとディープインパクトの日本レコードとさして違わない価値を認めたい。
2着に追いあげたトーセンジョーダン、3着に伸びてきたウインバリアシオンは、前半の1600m通過地点で先行のビートブラックから少なくとも20~25馬身あったから、推定1分40秒0近い前半の通過か。離して飛ばした先行馬のいなかった2006年のディープインパクト自身の前半1600m通過も、だいたい1分40秒0前後だった。推測なのでもちろん誤差はある。
したがって、トーセンジョーダン(岩田康誠騎手)、さらにそのあとにいたウインバリアシオン(武豊騎手)は、まさかビートブラックがそのままのペースを保って粘り込むとは思いもよらなかったが(ファンとも同じ)、2頭はディープインパクトではないから、あのペースで前半の1600mを通過した時点で、3分13秒台で乗り切ることは不可能である。
ビートブラックに4馬身、さらに2馬身の差をつけられての完敗は、対ビートブラックではなく、同じ位置にいて一気に進出して行ったディープインパクトを仮想の勝ち馬とすると分かりやすい。ディープインパクトのように3200mで上がり44秒台(推定5ハロン56秒台)など、それは不可能。だから、あの位置にいた時点で、どういう差し追い込み馬もディープインパクトのように3分13秒台は無理となった。
ところが、先行したビートブラックはまったく逆の戦い方で、芝状態を読み、レース前にはとても無理だろうと思えた高速の3200mを乗り切ってみせたのである。石橋脩騎手は、ふだん夢中になるとあまりにも鞭を連打しすぎるとされるが、この天皇賞・春のペース感覚と、スパート判断は、決して「イチかバチか」ではない。歴史的な好騎乗である。
長距離重賞で、評価の低い伏兵先行馬の逃げ込みを許したときの、人気の差し=追い込み馬の騎手の心情はつらい。つまるところ「ペース判断ができなかった。的確ではなかった」ということになるが、今回はビートブラック(石橋脩騎手)があまりに素晴らしすぎたから、仕方がない面もあるだろう。ただし、負けた人気上位馬の上がりは3200mのGIなのにまだみんな脚があった「33秒台~34秒0」である。どうみても前半あまりにタメ過ぎていたことは否定できない。
多くの人びとに、「いったいどうしたのだろう」。あまりにも残念なレースの印象を残し、むなしいチャンピオンを感じさせたオルフェーヴルは、すっかり人間不信に陥った悲しい馬のように映った。今度は「大丈夫」と思わせる動きをみせ、体つきも決して悪くはなかったが、それは天才オルフェーヴル(4冠馬)の虚勢だったかもしれない。パドックも悪くはなかった。でも、威厳とオ-ラがなかった。
阪神大賞典。自身が気負い過ぎたことは確かだが、再三再四、どう考えてもレースを止めるように指示されたのが信頼する池添謙一騎手であり、なんとか止めたら、また走れという。あのあとの中間、あまり好きでもないEコースで、みんなが息を詰めるように見つめる中で、調教再審査といういわれのない走法審査。みんなの自分を見つめる目が以前とはちがっている。信頼し、一番気心の知れているはずの人たちが「危険な馬」を見るように距離を置いている気がする。疲れとか、筋肉の動きとか、脚元がどうのとかではなく、「こころ」の動きを含めた体調が落ちていたとしか思えない。
自身満々に破格の3分02秒8で好位から抜け出した菊花賞3000mと同じような距離なのに、闘志に点火し、スパートを開始しなければならない勝負どころの2000m地点は、あの日より約「2秒」も遅い通過である。みんなはもっと先に行っている。オルフェーヴルは走っていて悲しかった。4コーナーで大きく外に回りかけたときには、もう明らかにオルフェーヴル自身があきらめていた。
1948年、長野県出身、早稲田大卒。1973年に日刊競馬に入社。UHFテレビ競馬中継解説者時代から、長年に渡って独自のスタンスと多様な角度からレースを推理し、競馬を語り続ける。netkeiba.com、競馬総合チャンネルでは、土曜メインレース展望(金曜18時)、日曜メインレース展望(土曜18時)、重賞レース回顧(月曜18時)の執筆を担当。
バックナンバー
新着コラム