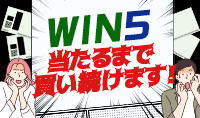夏競馬と夏祭り
- 2013年07月06日(土) 12時00分
- 23
日曜日に行われる七夕賞の出馬表を眺めていると、ある馬のところで目がとまった。
モンテエンである。
なぜこの馬が気になったのか、しばらく自分でもわからなかった。
――うーん、モンテエンねえ……。
牡6歳。父ゼンノロブロイ、母サンセットキス(母の父トニービン)。近親に1997年の青葉賞を勝ったトキオエクセレント、2003年の中京記念、大阪杯を連勝したタガノマイバッハなどがいる。
――なかなかの良血だな。
美浦・松山康久厩舎、馬主・毛利喜昭氏。
――ダービー2勝トレーナーと、「モンテ」の冠号で知られるオーナーの組み合わせか。
昨年12月のディセンバーステークス以来7か月ぶりの実戦。左前球節炎のため、ここまで待つことになった。ハンデは55キロ。
昨年、4か月ぶりとなった福島民報杯で3着と善戦している。
――この馬、休み明けでも走るんだな……あ、そうか!
モンテエンが私の目を惹いたのは、昨年の福島民報杯での走りが、頭の片隅の記憶のポケットに残っていたからのようだ。
「再開、そして再会。」これが昨春の福島競馬のテーマであり、キャッチコピーでもあった。
東日本大震災と東京電力福島第一原子力発電所事故の影響で開催ができなくなった福島競馬場で、昨年4月7日、1年5カ月ぶりに競馬が行われた。その日のメインレースが、モンテエンが3着になった福島民報杯だった。今年の七夕賞のメンバーのなかで、福島競馬が再開された日に現地で走った唯一の馬がモンテエンなのである。
福島に競馬が帰ってきてから1年と3カ月が経過した。震災からは2年と4カ月ほど。同じ福島でも原発に近い浜通りではなかなか復興が進まずにいるが、ともかく、49回目を迎える伝統のハンデ戦、七夕賞にフルゲートの16頭、それもなかなかの好メンバーが揃った。
ドバイ以来のトレイルブレイザー、重賞3勝馬ナリタクリスタル、去年の小倉記念でトーセンラーを下したエクスペディションといった実績馬のほか、小倉大賞典2着、新潟大賞典3着と好調のダコール、今年の福島民報杯を勝ったマイネルラクリマなど、勢いのある馬たちも面白そうだ。
そして、このモンテエン。先述したように、休み明けでも走るし、数を使われていないので馬齢のわりにフレッシュで、調教の動きもいい。55キロという動きやすいハンデなら、直線で一気に飛んでくるかもしれない。
七夕賞の時期になると夏競馬たけなわ、という感じがする。
七夕賞の翌日、7月8日からはセレクトセールが、その翌週にはセレクションセールが行われ、競馬界はフレッシュな賑わいの時期を迎える。
そして7月最後の土・日・月、今年の場合27、28、29日には、世界最大級の馬の祭り、相馬野馬追が行われる。
出陣用の飾りつけをした500頭以上の馬が、甲冑を着た侍を乗せて相馬市、南相馬市の街中を練り歩く騎馬武者行列。旗指物を背にした侍たちが周回コースで腕を競う甲冑競馬。騎馬武者たちが空高く打ち上げられた旗を奪い合う神旗争奪戦。そして、裸馬を神社の境内に追い込んで神前に奉納する野馬懸など、この祭りならではの「人馬一体」のダイナミック動きを見ることができる。
本稿でもたびたび繰り返してきたが、千年以上の伝統を持ち、飢饉のときも戦時中も、そして震災の年も途切れることのなかった、この相馬野馬追に出ている馬のほとんどが、元競走馬なのである。
かつては、開催日が7月23、24、25日と日にちで固定されていたので、週末と重ならなかったとき、南相馬出身の木幡初広騎手が甲冑競馬に参加したこともあったという。
私は、震災のあと、「被災馬」という言葉が使われるようになり、それに当てはまる多くの馬がいる地として相馬、南相馬を訪ね、野馬追を取材するようになった。
野馬追と聞いて、私がまず思い出すのは、祭りがハネたあとの光景だ。私はいつも自分のクルマで行っているのだが、車列の流れが急に遅くなったと思ったら、前のほうを騎馬武者を背にした馬が横切っている。その馬は不意に立ち止まり、道端に置かれた桶から水をガブガブ飲みはじめる。信号よりも馬優先、なのである。アスファルトのあちこちにボロが落ちていて、それが多い方向には馬を飼っている家も多いことがわかる。
自分のクルマのなかというのは日常そのものである。そのままの状態で非日常の世界を走り、何百年もタイムスリップしてきたかのような人馬を間近に見て、息づかいを感じられる――。
それがたまらなく心地好い。
「旅」や「祭り」で得られるものには、安堵と高揚、孤独感と一体感など両極端なものがあると思うのだが、そうしたものを3日間、たっぷり体内にとり入れることができるのが、私にとっての相馬野馬追である。
梅雨が明け、凄まじい熱暑のなかでの夏祭りなので、行かれるさいは、熱中症対策と日焼け対策をしっかりされるよう、念のため。
モンテエンである。
なぜこの馬が気になったのか、しばらく自分でもわからなかった。
――うーん、モンテエンねえ……。
牡6歳。父ゼンノロブロイ、母サンセットキス(母の父トニービン)。近親に1997年の青葉賞を勝ったトキオエクセレント、2003年の中京記念、大阪杯を連勝したタガノマイバッハなどがいる。
――なかなかの良血だな。
美浦・松山康久厩舎、馬主・毛利喜昭氏。
――ダービー2勝トレーナーと、「モンテ」の冠号で知られるオーナーの組み合わせか。
昨年12月のディセンバーステークス以来7か月ぶりの実戦。左前球節炎のため、ここまで待つことになった。ハンデは55キロ。
昨年、4か月ぶりとなった福島民報杯で3着と善戦している。
――この馬、休み明けでも走るんだな……あ、そうか!
モンテエンが私の目を惹いたのは、昨年の福島民報杯での走りが、頭の片隅の記憶のポケットに残っていたからのようだ。
「再開、そして再会。」これが昨春の福島競馬のテーマであり、キャッチコピーでもあった。
東日本大震災と東京電力福島第一原子力発電所事故の影響で開催ができなくなった福島競馬場で、昨年4月7日、1年5カ月ぶりに競馬が行われた。その日のメインレースが、モンテエンが3着になった福島民報杯だった。今年の七夕賞のメンバーのなかで、福島競馬が再開された日に現地で走った唯一の馬がモンテエンなのである。
福島に競馬が帰ってきてから1年と3カ月が経過した。震災からは2年と4カ月ほど。同じ福島でも原発に近い浜通りではなかなか復興が進まずにいるが、ともかく、49回目を迎える伝統のハンデ戦、七夕賞にフルゲートの16頭、それもなかなかの好メンバーが揃った。
ドバイ以来のトレイルブレイザー、重賞3勝馬ナリタクリスタル、去年の小倉記念でトーセンラーを下したエクスペディションといった実績馬のほか、小倉大賞典2着、新潟大賞典3着と好調のダコール、今年の福島民報杯を勝ったマイネルラクリマなど、勢いのある馬たちも面白そうだ。
そして、このモンテエン。先述したように、休み明けでも走るし、数を使われていないので馬齢のわりにフレッシュで、調教の動きもいい。55キロという動きやすいハンデなら、直線で一気に飛んでくるかもしれない。
七夕賞の時期になると夏競馬たけなわ、という感じがする。
七夕賞の翌日、7月8日からはセレクトセールが、その翌週にはセレクションセールが行われ、競馬界はフレッシュな賑わいの時期を迎える。
そして7月最後の土・日・月、今年の場合27、28、29日には、世界最大級の馬の祭り、相馬野馬追が行われる。
出陣用の飾りつけをした500頭以上の馬が、甲冑を着た侍を乗せて相馬市、南相馬市の街中を練り歩く騎馬武者行列。旗指物を背にした侍たちが周回コースで腕を競う甲冑競馬。騎馬武者たちが空高く打ち上げられた旗を奪い合う神旗争奪戦。そして、裸馬を神社の境内に追い込んで神前に奉納する野馬懸など、この祭りならではの「人馬一体」のダイナミック動きを見ることができる。
本稿でもたびたび繰り返してきたが、千年以上の伝統を持ち、飢饉のときも戦時中も、そして震災の年も途切れることのなかった、この相馬野馬追に出ている馬のほとんどが、元競走馬なのである。
かつては、開催日が7月23、24、25日と日にちで固定されていたので、週末と重ならなかったとき、南相馬出身の木幡初広騎手が甲冑競馬に参加したこともあったという。
私は、震災のあと、「被災馬」という言葉が使われるようになり、それに当てはまる多くの馬がいる地として相馬、南相馬を訪ね、野馬追を取材するようになった。
野馬追と聞いて、私がまず思い出すのは、祭りがハネたあとの光景だ。私はいつも自分のクルマで行っているのだが、車列の流れが急に遅くなったと思ったら、前のほうを騎馬武者を背にした馬が横切っている。その馬は不意に立ち止まり、道端に置かれた桶から水をガブガブ飲みはじめる。信号よりも馬優先、なのである。アスファルトのあちこちにボロが落ちていて、それが多い方向には馬を飼っている家も多いことがわかる。
自分のクルマのなかというのは日常そのものである。そのままの状態で非日常の世界を走り、何百年もタイムスリップしてきたかのような人馬を間近に見て、息づかいを感じられる――。
それがたまらなく心地好い。
「旅」や「祭り」で得られるものには、安堵と高揚、孤独感と一体感など両極端なものがあると思うのだが、そうしたものを3日間、たっぷり体内にとり入れることができるのが、私にとっての相馬野馬追である。
梅雨が明け、凄まじい熱暑のなかでの夏祭りなので、行かれるさいは、熱中症対策と日焼け対策をしっかりされるよう、念のため。
作家。1964年札幌生まれ。Number、優駿、うまレターほかに寄稿。著書に『誰も書かなかった武豊 決断』『消えた天才騎手 最年少ダービージョッキー・前田長吉の奇跡』(2011年度JRA賞馬事文化賞受賞作)など多数。netkeiba初出の小説『絆~走れ奇跡の子馬~』が2017年にドラマ化された。最新刊は競馬ミステリーシリーズ第6弾『ブリーダーズ・ロマン』。プロフィールイラストはよしだみほ画伯。バナーのポートレート撮影は桂伸也カメラマン。
関連サイト:島田明宏Web事務所
バックナンバー
新着コラム
-
【高松宮記念予想】日本の生産界が誇る歴史的サイアーラインに注目 今年はなんと6頭が出走
18時間前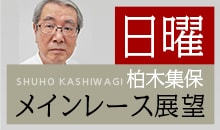
-
【高松宮記念予想】先週は70万オーバーのプラスと大活躍! 人気予想家がコラボした夢のAI予想に丸乗り!!
18時間前
-
【高松宮記念予想】大混戦で盲点に!? 過小評価される典型的なパターンを狙う/第226回
2025年03月29日(土) 12時00分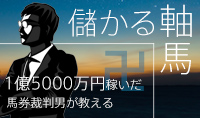
-
【高松宮記念】9回目のチャレンジで待望のGI制覇なるか スプリント王が顔をそろえた春の電撃戦を制すのは
2025年03月29日(土) 12時00分
-
【高松宮記念など予想】春のGI戦線が開幕! 長い直線を得意とする穴馬狙いで
2025年03月29日(土) 12時00分