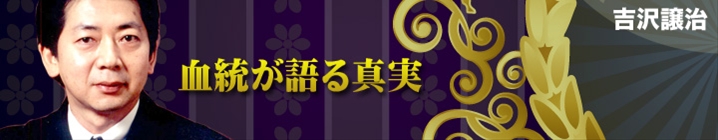
高齢種牡馬の“意地のひと花”
- 2013年11月15日(金) 12時00分
先週、東西で行われた2歳重賞のファンタジーS、京王杯2歳Sの優勝馬は、どちらも高齢種牡馬の父から生まれている。
ファンタジーSを勝ったベルカントの父サクラバクシンオーは、すでに2011年4月に22歳で死亡。その2か月前、三石の小さな牧場で生まれたのがベルカントだった。サクラバクシンオーが21歳時の種付けで出した産駒になる。
毎年、2歳戦で存在感を示してきたサクラバクシンオーだが、2010年のグランプリボス(朝日杯FS、京王杯2歳S)の活躍を最後に、勢いがトーンダウン。呼応するかのように古馬の短距離戦線でも、活躍馬がめっきり減っていた。
京王杯2歳Sを勝ったカラダレジェンドも、フレンチデピュティが18歳時の種付けで出した産駒である。数多くのGI勝ち馬を送り出してきたが、2010年のメイショウベルーガ(日経新春杯、京都大賞典、エリザベス女王杯2着)の活躍を最後に、こちらも重賞勝ち馬が途絶えていた。
面白いことに一流種牡馬は、高齢を迎えて人々が忘れかけたころになると、意地のひと花を咲かせることが多い。パーソロン晩年の傑作シンボリルドルフ(三冠馬)、シーホーク晩年の傑作アイネスフウジン(日本ダービー)などがそうだった。
昔の種付頭数は、多くて年間50頭前後。内国産種牡馬の成功例も少なかった。だから、一流種牡馬は高齢になってもそれはそれは大事に扱い、“最後の一滴”まで無駄にはしなかった。
だが、今は年間250頭の種付けが可能。サンデーサイレンス系を筆頭に、内国産種牡馬の成功も相次いでいる。このため種牡馬の世代交代が早く、17歳前後を迎えると第一線から外されていく。配合牝馬の数は維持しても、質はかなり落ちることが多い。
おそらく暮れの2歳戦や、来春のクラシック戦線が始まれば、ランキング上位の若い種牡馬が台頭してくるのだろう。しかしサクラバクシンオー、フレンチデピュティの活躍は、そんな“姥捨て”が進行する風潮に対する蜂の一刺し、ささやかな抵抗と言えなくもない。
ファンタジーSを勝ったベルカントの父サクラバクシンオーは、すでに2011年4月に22歳で死亡。その2か月前、三石の小さな牧場で生まれたのがベルカントだった。サクラバクシンオーが21歳時の種付けで出した産駒になる。
毎年、2歳戦で存在感を示してきたサクラバクシンオーだが、2010年のグランプリボス(朝日杯FS、京王杯2歳S)の活躍を最後に、勢いがトーンダウン。呼応するかのように古馬の短距離戦線でも、活躍馬がめっきり減っていた。
京王杯2歳Sを勝ったカラダレジェンドも、フレンチデピュティが18歳時の種付けで出した産駒である。数多くのGI勝ち馬を送り出してきたが、2010年のメイショウベルーガ(日経新春杯、京都大賞典、エリザベス女王杯2着)の活躍を最後に、こちらも重賞勝ち馬が途絶えていた。
面白いことに一流種牡馬は、高齢を迎えて人々が忘れかけたころになると、意地のひと花を咲かせることが多い。パーソロン晩年の傑作シンボリルドルフ(三冠馬)、シーホーク晩年の傑作アイネスフウジン(日本ダービー)などがそうだった。
昔の種付頭数は、多くて年間50頭前後。内国産種牡馬の成功例も少なかった。だから、一流種牡馬は高齢になってもそれはそれは大事に扱い、“最後の一滴”まで無駄にはしなかった。
だが、今は年間250頭の種付けが可能。サンデーサイレンス系を筆頭に、内国産種牡馬の成功も相次いでいる。このため種牡馬の世代交代が早く、17歳前後を迎えると第一線から外されていく。配合牝馬の数は維持しても、質はかなり落ちることが多い。
おそらく暮れの2歳戦や、来春のクラシック戦線が始まれば、ランキング上位の若い種牡馬が台頭してくるのだろう。しかしサクラバクシンオー、フレンチデピュティの活躍は、そんな“姥捨て”が進行する風潮に対する蜂の一刺し、ささやかな抵抗と言えなくもない。
血統評論家。月刊誌、週刊誌の記者を経てフリーに。著書「競馬の血統学〜サラブレッドの進化と限界」で1998年JRA馬事文化賞を受賞。「最強の血統学」、「競馬の血統学2〜母のちから」、「サラブレッド血統事典」など著書多数。




