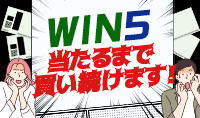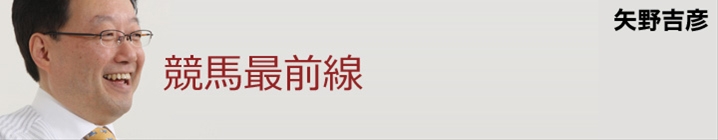
競馬は“時代を映す鏡”
- 2014年08月30日(土) 12時00分
- 12
日本競馬の栄枯盛衰を分析
“時代を映す鏡”という言葉があります。インターネットで検索すると、映画、文学、広告などが“鏡”の例として挙げられています。もちろん、それだけではありません。競馬も、時代、あるいはその国や地域の特色を映し出す“鏡”だと思いませんか?高度成長期やバブルの時代にはジャンジャン売れていた馬券が、経済の衰退とともに潮が引くように売れなくなり、地方競馬場が廃止に追い込まれていきました。日本経済の実態が競馬に色濃く反映されているのです。
さらにもうひとつ、競馬と並ぶ“鏡”を発見してしまいました。それは、「夏の甲子園に出場した公立商業高校の数」。「また高校野球ネタか?」なんて言わずに、ちょっとだけお付き合いください。
夏の甲子園が常時“1県1校”(東京と北海道は2校)出場になったのは1978年(昭和53年)の第60回大会から。この年は8つの公立商業高校が甲子園に駒を進めました。中でも四国は、香川・高松商、愛媛・松山商、徳島商、高知商と史上唯一の“4県揃い踏み”。以降、87年まで毎年7校以上が出場を果たします。
そして88年の第70回大会では、群馬・高崎商、静岡・浜松商、岐阜・大垣商、富山商、福井商、滋賀・八幡商、岡山・倉敷商、広島商、山口・宇部商、香川・坂出商、愛媛・松山商、高知商、佐賀商の計13校が甲子園に出場しました。これは“1県1校”になってからの最多記録。言い換えれば、時代の転換点になっているわけです。ちなみに88年(昭和63年)といえばバブル経済絶頂期。ところが、同年3月に紀三井寺競馬場が廃止されています。これも、今考えればその後の”退潮”を暗示させる転換点でした。
話を戻します。89、90年は8校が出場し、78年以来13大会連続で7校以上のラインをキープしていた公立商業高校勢ですが、バブルがはじけ始めた91年は6校、崩壊したとされる92年には3校にまで急減。その後何度か増減を繰り返したものの、92~01年の10年間では、3校しか出場できなかった年が4回を数え、潮目が変わってしまいました。付け加えれば、4度目の3校出場となった01年は、中津競馬場が廃止された年。ここから各地の地方競馬も続々と廃止されていきます。
それから先は、06年に7校が出場したのが最多。春夏どちらかの大会で優勝経験のある学校の出場も07年の徳島商を最後に途絶え、今年はついに史上最小の2校出場にまで落ち込んでしまいました。
「夏の甲子園に出場した公立商業高校の数」の推移と、日本競馬の栄枯盛衰の流れは、見事に連動しているような気がします。それが“時代(経済)を映す鏡”だとすれば、今年の出場校数が2校にまで減ってしまったというのは由々しき事態。馬券売り上げが復調傾向にあるとはいうものの、安心してはいられないのかもしれません。
テレビ東京「ウイニング競馬」の実況を担当するフリーアナウンサー。中央だけでなく、地方、ばんえい、さらに海外にも精通する競馬通。著書には「矢野吉彦の世界競馬案内」など。
バックナンバー
新着コラム
-
【高松宮記念予想】日本の生産界が誇る歴史的サイアーラインに注目 今年はなんと6頭が出走
22時間前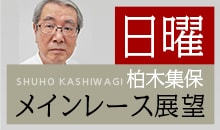
-
【高松宮記念予想】先週は70万オーバーのプラスと大活躍! 人気予想家がコラボした夢のAI予想に丸乗り!!
22時間前
-
【高松宮記念予想】大混戦で盲点に!? 過小評価される典型的なパターンを狙う/第226回
2025年03月29日(土) 12時00分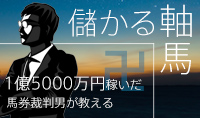
-
【高松宮記念】9回目のチャレンジで待望のGI制覇なるか スプリント王が顔をそろえた春の電撃戦を制すのは
2025年03月29日(土) 12時00分
-
【高松宮記念など予想】春のGI戦線が開幕! 長い直線を得意とする穴馬狙いで
2025年03月29日(土) 12時00分