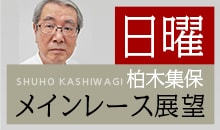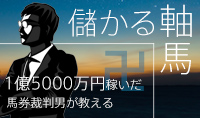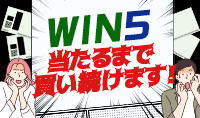公正競馬と調整ルーム
- 2024年06月06日(木) 12時00分
- 94
先日、水沼元輝騎手が、調整ルームにスマートフォンを持ち込み、使用していた事実が判明したとして、騎乗停止となることが発表された。専用ロッカーに預けたかのように装うためケースのみをロッカーに入れ、調整ルーム内で飲食店を予約したり、TikTokを見たりしていたという。
昨春、のちに「スマホシックス」と呼ばれる6人の若手騎手が開催日にスマホを使用し、30日間(開催10日間)の騎乗停止になったばかりだけに、残念である。
なぜ同じようなことが、同じような世代の騎手によって繰り返されるのか。
調整ルームでの通信禁止は、たかがルールで、そもそもルール自体が古臭く、主催者が騎手を管理しやすくするために存在しているものであり、まともなルールではない――といったようにとらえているからではないか。
古いのは確かである。競馬法が制定されたのは1923(大正12)年。昨年、競馬法制定100周年を記念したレースやイベントが行われたことは記憶に新しい。競馬法の制定により、馬券の発売が正式に認められた。それ以前は、主催者が不正に走ったり、馬券の借金で家を傾ける人間が現れたりと、競馬の存在そのものが社会問題になり、馬券の発売が禁止されていた。だからこそ、競馬法に則した公正な運営が絶対条件になったのである。
また、騎手たちが調整ルームに入って外部との接触を断つようになったのは、1965(昭和40)年に起きた不正事件「山岡事件」がきっかけとされており、これも60年近く前と、ずいぶん古い話である。しかし、調整ルームやジョッキールームは、保田隆芳元騎手が、1958(昭和33)年にハクチカラとともに戦後初の海外遠征としてアメリカに渡り、帰国後、主催者に進言してつくられたものだ。当時、日本の騎手の地位はアメリカなどに比べると低く、競馬場内に勝負服を着替える場所すらなかった。そこで、騎手専用のスペースが設けられることになったのだ。
保田氏は、前述したアメリカ遠征で習得したモンキー乗りを日本にひろめたことで知られている。それにより、日本の騎手の騎乗技術は飛躍的に進化したわけだが、調整ルームとジョッキールームも、モンキー乗りと同じく、保田氏が日本の騎手を世界水準へとアップデートさせるために持ち込んだ「プラスの遺産」だったのだ。
ところが、今は、騎手を拘束して主催者が管理しやすくするためのシステムとしか見られていない。確かに、日本の競馬は「管理競馬」とも言われ、レースの10日前までにJRAの施設に入厩しなければいけない「10日競馬」もそのひとつだ。しかし、これらは管理のための管理ではなく、あくまでも、公正競馬のための管理なのである。
なぜそこまで公正確保に注力しなければならないのかというと、日本では公営ギャンブル以外の賭博が禁じられているなか、前述したような負の歴史があるからだ。競馬は、明治末期からの「馬券禁止時代」のみならず、競馬法制定後も「競馬賭博」と呼ばれ、一般社会から関係者やファンが白眼視された時期があった。「あった」と過去形にすべきではないかもしれない。
そうした状況を憂い、「ミスター競馬」野平祐二氏は、競馬のスポーツとしての魅力を発信すべく、自ら広告塔となって積極的にメディアに登場したり、多くの文化人を自宅の「野平サロン」に招いたりと、馬に乗ること以外でも力を尽くした。ミスターのような先人たちがいたことを忘れてはならない。
だが、動物愛護や環境保護の立場から、競馬の存続に本気で反対している人間たちは国内外に一定数いる。鞭の使用回数が制限されるようになったのも、そうした方面からの圧力の結果である。
鞭の使い方を制限するルールの制定は、競馬以外のギャンブルが認められているヨーロッパのほうが早かった。競馬の存続に反対する勢力が日本より強いからということもあるのだろうが、日本だって、戦後、現行の競馬法が成立した1948(昭和23)年以降も、競馬に反対する大きな声が、野党やPTAなどから上がった時期もあった。
繰り返しになるが、公営ギャンブル以外は御法度の国だからこそ、ここまで厳正な運営に徹し、公正であることを前面に押し出す結果となっている。それには、誰の目にも明らかな具体例が必要で、そのひとつが、「騎手たちが調整ルームに入り、外部との接触を遮断すること」なのである。
JRAに関して言えば、山岡事件が起きたころと違い、賞金がこれだけ高くなると、小金のために八百長に走ろうとする者はまず現れない。それでも、「李下に冠を正さず」の考え方で、「我々はここまでして公正競馬に徹しています」と示すことは、今なお必要だと、少なくとも私は思う。
もし、政権交代がなされるなど日本の政治の風向きが変わり、IR計画が中止となり、ギャンブル依存症対策の流れで競馬法が見直され、馬券を売らない競馬のみ存続を認められるようになったらどうなるか。
運営のための原資は、国からの補助金、入場料、放映権料をはじめとするロイヤルティなどに頼ることになる。賞金は馬主の持ち寄りか。そうなるとすべての前提条件が崩れ、前述した「賞金がこれだけ高くなると」といったこともなくなる。馬の価格は暴落し、1頭あたり月70万円ほどと言われている預託料は数万円になり、トップジョッキーでも年収1千万円かそこら。すぐにパートI国から陥落し、サンデー系の良質な種牡馬や繁殖牝馬はどんどん海外に流出するだろう。レベルの下がった日本のレースの馬券を自国で売りたいという海外の主催者もいなくなるだろうから、手数料収入も望めない。馬券を売らないと、いかに競馬関係者が苦境に陥るかは歴史が証明している。
まあ、これは極端な例で、ここまで凋落することはないかもしれないが、ともかく、現状のまま正常進化していくことが望ましいという考えは間違っていないと思う。
ただ、先述したように、競馬法ができたのも、現行の競馬法による運営になったのも、調整ルームに騎手が缶詰にされるようになったのも、ずいぶん前のことで、時代は大きく変わっている。情報の流れ方も劇的に変化している。
それに合わせ、公正であることの示し方も変わってきていいと私は思っていた。
2015年から海外のレースの馬券が売られるようになった。当たり前だが、海外のレースに臨む騎手たちは、レース前日から調整ルームに入っていたわけではない。従前の公正確保とは別のプロセスでなされるレースの馬券を売るようになったのだから、日本のレースにおける公正確保のプロセスが見直されるのはごく自然な流れと言えるだろう。
コロナ禍における「認定調整ルーム」も、大きなヒントとなった。
先日、武豊騎手の自宅が窃盗被害にあったが、それは金曜の夜と土曜の夜、騎手は自宅にいないことを知っていたうえでの犯行だったはずだ。日本で「水と安全はタダ」と言われた時代は終った。
調整ルームのあり方を、考え直してもいい時期に来ている。と、想像だが、主催者サイドも考えていたのではないか。折しも、競馬法100周年という節目を迎えていた。時代が変わったことを内外に示しながら、新たな施策を講じる絶好機と言えた。
ところが、昨春、今春と、一般ニュースにもなる残念な事案が起きてしまった。
腰を折られたことは確かだが、それでも、調整ルームには、入りたい騎手だけが入る、という方向への転換がなされてもいいのではないか。それが、前述した海外のレースと条件を近づけることにもなる。初めて調整ルームに入った外国人騎手のなかには、リラックスすることも、集中することもできてとてもいい、と喜んでいた人もいると聞いた。最初は、「認定調整ルーム」の拡大解釈ということになるのかもしれないが、敬愛する保田先生が望んだ、本来の調整ルームになってくれると、競馬ファンであり、保田隆芳ファンでもある私は嬉しい。
昨春、のちに「スマホシックス」と呼ばれる6人の若手騎手が開催日にスマホを使用し、30日間(開催10日間)の騎乗停止になったばかりだけに、残念である。
なぜ同じようなことが、同じような世代の騎手によって繰り返されるのか。
調整ルームでの通信禁止は、たかがルールで、そもそもルール自体が古臭く、主催者が騎手を管理しやすくするために存在しているものであり、まともなルールではない――といったようにとらえているからではないか。
古いのは確かである。競馬法が制定されたのは1923(大正12)年。昨年、競馬法制定100周年を記念したレースやイベントが行われたことは記憶に新しい。競馬法の制定により、馬券の発売が正式に認められた。それ以前は、主催者が不正に走ったり、馬券の借金で家を傾ける人間が現れたりと、競馬の存在そのものが社会問題になり、馬券の発売が禁止されていた。だからこそ、競馬法に則した公正な運営が絶対条件になったのである。
また、騎手たちが調整ルームに入って外部との接触を断つようになったのは、1965(昭和40)年に起きた不正事件「山岡事件」がきっかけとされており、これも60年近く前と、ずいぶん古い話である。しかし、調整ルームやジョッキールームは、保田隆芳元騎手が、1958(昭和33)年にハクチカラとともに戦後初の海外遠征としてアメリカに渡り、帰国後、主催者に進言してつくられたものだ。当時、日本の騎手の地位はアメリカなどに比べると低く、競馬場内に勝負服を着替える場所すらなかった。そこで、騎手専用のスペースが設けられることになったのだ。
保田氏は、前述したアメリカ遠征で習得したモンキー乗りを日本にひろめたことで知られている。それにより、日本の騎手の騎乗技術は飛躍的に進化したわけだが、調整ルームとジョッキールームも、モンキー乗りと同じく、保田氏が日本の騎手を世界水準へとアップデートさせるために持ち込んだ「プラスの遺産」だったのだ。
ところが、今は、騎手を拘束して主催者が管理しやすくするためのシステムとしか見られていない。確かに、日本の競馬は「管理競馬」とも言われ、レースの10日前までにJRAの施設に入厩しなければいけない「10日競馬」もそのひとつだ。しかし、これらは管理のための管理ではなく、あくまでも、公正競馬のための管理なのである。
なぜそこまで公正確保に注力しなければならないのかというと、日本では公営ギャンブル以外の賭博が禁じられているなか、前述したような負の歴史があるからだ。競馬は、明治末期からの「馬券禁止時代」のみならず、競馬法制定後も「競馬賭博」と呼ばれ、一般社会から関係者やファンが白眼視された時期があった。「あった」と過去形にすべきではないかもしれない。
そうした状況を憂い、「ミスター競馬」野平祐二氏は、競馬のスポーツとしての魅力を発信すべく、自ら広告塔となって積極的にメディアに登場したり、多くの文化人を自宅の「野平サロン」に招いたりと、馬に乗ること以外でも力を尽くした。ミスターのような先人たちがいたことを忘れてはならない。
だが、動物愛護や環境保護の立場から、競馬の存続に本気で反対している人間たちは国内外に一定数いる。鞭の使用回数が制限されるようになったのも、そうした方面からの圧力の結果である。
鞭の使い方を制限するルールの制定は、競馬以外のギャンブルが認められているヨーロッパのほうが早かった。競馬の存続に反対する勢力が日本より強いからということもあるのだろうが、日本だって、戦後、現行の競馬法が成立した1948(昭和23)年以降も、競馬に反対する大きな声が、野党やPTAなどから上がった時期もあった。
繰り返しになるが、公営ギャンブル以外は御法度の国だからこそ、ここまで厳正な運営に徹し、公正であることを前面に押し出す結果となっている。それには、誰の目にも明らかな具体例が必要で、そのひとつが、「騎手たちが調整ルームに入り、外部との接触を遮断すること」なのである。
JRAに関して言えば、山岡事件が起きたころと違い、賞金がこれだけ高くなると、小金のために八百長に走ろうとする者はまず現れない。それでも、「李下に冠を正さず」の考え方で、「我々はここまでして公正競馬に徹しています」と示すことは、今なお必要だと、少なくとも私は思う。
もし、政権交代がなされるなど日本の政治の風向きが変わり、IR計画が中止となり、ギャンブル依存症対策の流れで競馬法が見直され、馬券を売らない競馬のみ存続を認められるようになったらどうなるか。
運営のための原資は、国からの補助金、入場料、放映権料をはじめとするロイヤルティなどに頼ることになる。賞金は馬主の持ち寄りか。そうなるとすべての前提条件が崩れ、前述した「賞金がこれだけ高くなると」といったこともなくなる。馬の価格は暴落し、1頭あたり月70万円ほどと言われている預託料は数万円になり、トップジョッキーでも年収1千万円かそこら。すぐにパートI国から陥落し、サンデー系の良質な種牡馬や繁殖牝馬はどんどん海外に流出するだろう。レベルの下がった日本のレースの馬券を自国で売りたいという海外の主催者もいなくなるだろうから、手数料収入も望めない。馬券を売らないと、いかに競馬関係者が苦境に陥るかは歴史が証明している。
まあ、これは極端な例で、ここまで凋落することはないかもしれないが、ともかく、現状のまま正常進化していくことが望ましいという考えは間違っていないと思う。
ただ、先述したように、競馬法ができたのも、現行の競馬法による運営になったのも、調整ルームに騎手が缶詰にされるようになったのも、ずいぶん前のことで、時代は大きく変わっている。情報の流れ方も劇的に変化している。
それに合わせ、公正であることの示し方も変わってきていいと私は思っていた。
2015年から海外のレースの馬券が売られるようになった。当たり前だが、海外のレースに臨む騎手たちは、レース前日から調整ルームに入っていたわけではない。従前の公正確保とは別のプロセスでなされるレースの馬券を売るようになったのだから、日本のレースにおける公正確保のプロセスが見直されるのはごく自然な流れと言えるだろう。
コロナ禍における「認定調整ルーム」も、大きなヒントとなった。
先日、武豊騎手の自宅が窃盗被害にあったが、それは金曜の夜と土曜の夜、騎手は自宅にいないことを知っていたうえでの犯行だったはずだ。日本で「水と安全はタダ」と言われた時代は終った。
調整ルームのあり方を、考え直してもいい時期に来ている。と、想像だが、主催者サイドも考えていたのではないか。折しも、競馬法100周年という節目を迎えていた。時代が変わったことを内外に示しながら、新たな施策を講じる絶好機と言えた。
ところが、昨春、今春と、一般ニュースにもなる残念な事案が起きてしまった。
腰を折られたことは確かだが、それでも、調整ルームには、入りたい騎手だけが入る、という方向への転換がなされてもいいのではないか。それが、前述した海外のレースと条件を近づけることにもなる。初めて調整ルームに入った外国人騎手のなかには、リラックスすることも、集中することもできてとてもいい、と喜んでいた人もいると聞いた。最初は、「認定調整ルーム」の拡大解釈ということになるのかもしれないが、敬愛する保田先生が望んだ、本来の調整ルームになってくれると、競馬ファンであり、保田隆芳ファンでもある私は嬉しい。
作家。1964年札幌生まれ。Number、優駿、うまレターほかに寄稿。著書に『誰も書かなかった武豊 決断』『消えた天才騎手 最年少ダービージョッキー・前田長吉の奇跡』(2011年度JRA賞馬事文化賞受賞作)など多数。netkeiba初出の小説『絆~走れ奇跡の子馬~』が2017年にドラマ化された。最新刊は競馬ミステリーシリーズ第6弾『ブリーダーズ・ロマン』。プロフィールイラストはよしだみほ画伯。バナーのポートレート撮影は桂伸也カメラマン。
関連サイト:島田明宏Web事務所