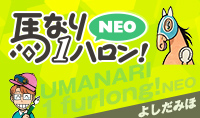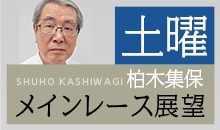勢司和浩調教師 Part5 プロの仕事
- 2007年11月07日(水) 20時20分
- 0
勢司和浩調教師はウッドチップにおける効果を熟知している。それでも、管理馬たちはダートコースをメインに調教を行なっている(坂路と芝コースを併用しながらではあるが)。

ウッドチップが主流となっている時代になぜ。言葉は悪いが、時代の流れに逆行しているような印象を受けるのだが、なぜダートなのか。
「いま世界中を見ても、ウッドチップが使われている国は逆に激減し、ほとんどないというくらいになってきているんです。たしかにウッドチップには、筋肉や腱に負荷を与える効果がありますが、逆に言えばハードな調教に耐えられない弱い馬を調教したならば、大きなアクシデントにつながる可能性が大きくなるわけですよ。例えば、骨が弱い馬は、ダートならソエで済むところが、ウッドならば第一支骨骨折というように、被害が拡大してしまう傾向が強い。実際、これまでにちょっとしたミスステップで競走能力喪失という結果になってしまった馬たちがいました。すべては彼らが教えてくれたことなんですよ」
勢司師は、競走馬として再起不能になった管理馬たちとの実体験に向き合った結果として、ダートでの調教を行なっている。だが実は、ダートでの調教を主体としている理由がもうひとつあることを明かしてくれた。
「それは乗り手の技術向上にあるのです。ウチの先生(国枝栄調教師)も言ってましたけれど、坂路を使用して調教すれば素人でも馬は仕上がっていくのは事実です。逆に言えば、乗り手の技術が要求されるのはダートということです。馬の前進気勢を人間が促さなければならない。別の言い方をすると人間が馬をその気にさせなければいけない。ですから、やる気のない人間ではダメで、いくら調教をしても息遣いもできてきませんから、競走馬になりません。つまり、ダートでしっかりと調教するためには、馬をしっかりとコントロールでき、その気にさせることができる技術が求められるのです。我々は勝つことと同時に、プロの乗り手を育てていかなければならないと思うんですよ。長い目で見れば、プロ、本物のホースマンを育てることが、安定した厩舎経営はもちろん、日本の競馬界にとって必ず必要なことではないでしょうか。たしかに、坂路やウッドチップでの調教はより楽に効果を得られます。しかし根本は、乗り手が馬をキッチリとコントロールして、そして一番大切な馬の前進気勢、つまりやる気を人間が促すというものです。決して簡単に習得できるものではない技術が求められるのがダートですが、我々はプロなんですから」
調教師としてのビジョンを言葉に込める勢司師。それをさらに表わすような出来事が先日もあった。毎日のように1時間30分近く馬場で乗り続けられる馬がいる。じっくりというよりも、徹底的に馬場で常脚をし続けていたのだ。
「すべて最初の2Fを、馬のわがままで行かせないためです。もし、普通に調教したならば、彼女の意思のままに、恐らく12から11秒くらいで行ってしまい、最後は歩いてしまうことになりますから。まして、最後にステッキを入れたらプレッシャーとなってしまい、さらにわがままを助長することになってしまう。もし馬の意思のままに競馬をしたらどうなりますか。いかに、最初の2Fをこちらのコントロール下で進み、しかも最後は前進気勢を保ったまましっかりとした脚取りで走り抜けることができるか。調教でできないのに、競馬でできるということはありませんから、だからこそ普段の調教が大切ですし、乗り手に従わなければならない、という基本をしっかり教え込まなければならないんですよ」
高いレベルを求めるからこそ、基本が何よりも大事と勢司師は繰り返すのであった。
続く
 勢司和浩 (せいし かずひろ) 美浦所属
勢司和浩 (せいし かずひろ) 美浦所属
船橋競馬場の厩務員を経て単身アイルランドへ競馬留学。名馬ニジンスキーを手掛けるヴィンセント・オブライエン厩舎で2年間の修行を積み、日本へ帰国後は昭和61年から美浦・稗田敏男厩舎、平成2年から美浦・国枝栄厩舎で調教助手を経験。平成11年から美浦トレーニングセンターの調教師となる。02年スマイルトゥモローでオークスを制し、GI初勝利を挙げた若手調教師。
★有力馬が続々登場のジャパンC特集はこちら!!★

ウッドチップが主流となっている時代になぜ。言葉は悪いが、時代の流れに逆行しているような印象を受けるのだが、なぜダートなのか。
「いま世界中を見ても、ウッドチップが使われている国は逆に激減し、ほとんどないというくらいになってきているんです。たしかにウッドチップには、筋肉や腱に負荷を与える効果がありますが、逆に言えばハードな調教に耐えられない弱い馬を調教したならば、大きなアクシデントにつながる可能性が大きくなるわけですよ。例えば、骨が弱い馬は、ダートならソエで済むところが、ウッドならば第一支骨骨折というように、被害が拡大してしまう傾向が強い。実際、これまでにちょっとしたミスステップで競走能力喪失という結果になってしまった馬たちがいました。すべては彼らが教えてくれたことなんですよ」
勢司師は、競走馬として再起不能になった管理馬たちとの実体験に向き合った結果として、ダートでの調教を行なっている。だが実は、ダートでの調教を主体としている理由がもうひとつあることを明かしてくれた。
「それは乗り手の技術向上にあるのです。ウチの先生(国枝栄調教師)も言ってましたけれど、坂路を使用して調教すれば素人でも馬は仕上がっていくのは事実です。逆に言えば、乗り手の技術が要求されるのはダートということです。馬の前進気勢を人間が促さなければならない。別の言い方をすると人間が馬をその気にさせなければいけない。ですから、やる気のない人間ではダメで、いくら調教をしても息遣いもできてきませんから、競走馬になりません。つまり、ダートでしっかりと調教するためには、馬をしっかりとコントロールでき、その気にさせることができる技術が求められるのです。我々は勝つことと同時に、プロの乗り手を育てていかなければならないと思うんですよ。長い目で見れば、プロ、本物のホースマンを育てることが、安定した厩舎経営はもちろん、日本の競馬界にとって必ず必要なことではないでしょうか。たしかに、坂路やウッドチップでの調教はより楽に効果を得られます。しかし根本は、乗り手が馬をキッチリとコントロールして、そして一番大切な馬の前進気勢、つまりやる気を人間が促すというものです。決して簡単に習得できるものではない技術が求められるのがダートですが、我々はプロなんですから」
調教師としてのビジョンを言葉に込める勢司師。それをさらに表わすような出来事が先日もあった。毎日のように1時間30分近く馬場で乗り続けられる馬がいる。じっくりというよりも、徹底的に馬場で常脚をし続けていたのだ。
「すべて最初の2Fを、馬のわがままで行かせないためです。もし、普通に調教したならば、彼女の意思のままに、恐らく12から11秒くらいで行ってしまい、最後は歩いてしまうことになりますから。まして、最後にステッキを入れたらプレッシャーとなってしまい、さらにわがままを助長することになってしまう。もし馬の意思のままに競馬をしたらどうなりますか。いかに、最初の2Fをこちらのコントロール下で進み、しかも最後は前進気勢を保ったまましっかりとした脚取りで走り抜けることができるか。調教でできないのに、競馬でできるということはありませんから、だからこそ普段の調教が大切ですし、乗り手に従わなければならない、という基本をしっかり教え込まなければならないんですよ」
高いレベルを求めるからこそ、基本が何よりも大事と勢司師は繰り返すのであった。
続く
船橋競馬場の厩務員を経て単身アイルランドへ競馬留学。名馬ニジンスキーを手掛けるヴィンセント・オブライエン厩舎で2年間の修行を積み、日本へ帰国後は昭和61年から美浦・稗田敏男厩舎、平成2年から美浦・国枝栄厩舎で調教助手を経験。平成11年から美浦トレーニングセンターの調教師となる。02年スマイルトゥモローでオークスを制し、GI初勝利を挙げた若手調教師。
★有力馬が続々登場のジャパンC特集はこちら!!★