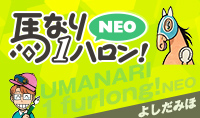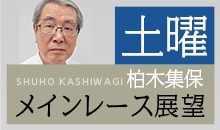勢司和浩調教師 Part6 「アスリート」か「高価な商品」か
- 2007年11月14日(水) 23時49分
- 0
毎日速いキャンターを行なうべく、敢えて馬のメンタル面、そして基礎体力に拘る勢司和浩調教師は、「すべては競馬で勝つためですから」と言い切る。

「競馬を勝つということは決して簡単じゃありません。新馬戦を勝ったのに、そのあとまったく走らなくなるという馬がいますが、そのひとつの理由としてパニックを起こした可能性が考えられます。ワケがわからなくなって、危険を回避するという本能がそうさせるのですけれど、一度経験することで競馬というモノを理解してしまいますから。逆に、苦しい経験をしたことで、走らされることを拒絶するようになってしまいかねない。そもそも、馬たちは持てる力の100%を出し切っているわけではないのです。だからこそ、馬の意志の表れである前進気勢が旺盛であるべきで、それを人間がいかにコントロールできるかということが課題なんですよ。そのために、馴致、そしてしっかりとコンタクトが取れたダク、そしてキャンターが必要不可欠なんです。調教でできないモノが、より緊張状態が増す競馬でできるわけがありません」
強い馬をつくり、そして競馬に勝つために、より高いレベルを目指し続ける勢司師だが、「近年は馬が弱くなってきています」という現実を口にする。
実は、そのような言葉は勢司師以外の調教師たちの口からも耳にする機会が増えている。特に「肉体面」という指摘が多いのだが、以前と比べ、馬の主食である放牧地の牧草は土壌改良が繰り返されているため、それこそ人間に負けないほどの飼養管理がなされるようになったとされる。それがなぜ、弱くなっているというのだろうか。
「たしかに育成者の方々、そして生産者の方々は相当研究し、レベルアップされてきています。いかに飼養管理が良くなっているか、馬たちの体をみればハッキリとわかりますからね。幼い頃から管理され、栄養価の高い飼料が与えられているのです。実際、ひと昔前と比べれば明らかに馬っぷりは良くなりました。マーケットブリーダーの方々にとっては当然のことで、より良い値段で売るためには必要なことなのです。現実に日本のマーケットをみても、そういう馬たちに高い値が付けられていますから。ただ、偽らざる感触を言わせてもらうのならば、そういう傾向が強くなるのと反比例するように、馬がどんどん弱くなっています」
人間の世界でも食文化の欧米化などにより、体型や骨の強度など様々な変化が生まれてきていることが伝えられている。その現実に「そう、人間と同じなのです」と勢司師は頷く。
「アメリカのセールなどでは、とても1歳馬とは思えないような馬っぷりの馬たちが多く見られます。そこには徹底的な飼養管理がなされるなど、より高く売るための馬づくりというものがあるのです。それがいまでは、日本、そして馬は自然であるべきという考え方が支配していたヨーロッパのセールでも、馬をつくり始めているのが現実なのです」
では、具体的にどのような変化が問題なのだろうか。勢司師は、その答えを“肥満”だと言う。
「骨の強さをはじめ、全体的に弱くなっているのですが、“太りすぎ”に原因があると思います。人間でも問題になっていますが、幼い頃から栄養価の高い飼料を口にすることによって肉付きは良くなりますが、そうなればその分馬は動かなくなりますから。つまりは飼養管理されることで運動不足に陥りやすいということなのです」
勢司師をはじめ多くのトレーナーたちが感じている「馬が弱くなった」という感触は、アスリートであるべき競走馬が、一方では高い値が付けられる“高価な商品”というもうひとつの側面が生み出していることなのだ。
続く
 勢司和浩 (せいし かずひろ) 美浦所属
勢司和浩 (せいし かずひろ) 美浦所属
船橋競馬場の厩務員を経て単身アイルランドへ競馬留学。名馬ニジンスキーを手掛けるヴィンセント・オブライエン厩舎で2年間の修行を積み、日本へ帰国後は昭和61年から美浦・稗田敏男厩舎、平成2年から美浦・国枝栄厩舎で調教助手を経験。平成11年から美浦トレーニングセンターの調教師となる。02年スマイルトゥモローでオークスを制し、GI初勝利を挙げた若手調教師。
★有力馬が続々登場のジャパンC特集はこちら!!★

「競馬を勝つということは決して簡単じゃありません。新馬戦を勝ったのに、そのあとまったく走らなくなるという馬がいますが、そのひとつの理由としてパニックを起こした可能性が考えられます。ワケがわからなくなって、危険を回避するという本能がそうさせるのですけれど、一度経験することで競馬というモノを理解してしまいますから。逆に、苦しい経験をしたことで、走らされることを拒絶するようになってしまいかねない。そもそも、馬たちは持てる力の100%を出し切っているわけではないのです。だからこそ、馬の意志の表れである前進気勢が旺盛であるべきで、それを人間がいかにコントロールできるかということが課題なんですよ。そのために、馴致、そしてしっかりとコンタクトが取れたダク、そしてキャンターが必要不可欠なんです。調教でできないモノが、より緊張状態が増す競馬でできるわけがありません」
強い馬をつくり、そして競馬に勝つために、より高いレベルを目指し続ける勢司師だが、「近年は馬が弱くなってきています」という現実を口にする。
実は、そのような言葉は勢司師以外の調教師たちの口からも耳にする機会が増えている。特に「肉体面」という指摘が多いのだが、以前と比べ、馬の主食である放牧地の牧草は土壌改良が繰り返されているため、それこそ人間に負けないほどの飼養管理がなされるようになったとされる。それがなぜ、弱くなっているというのだろうか。
「たしかに育成者の方々、そして生産者の方々は相当研究し、レベルアップされてきています。いかに飼養管理が良くなっているか、馬たちの体をみればハッキリとわかりますからね。幼い頃から管理され、栄養価の高い飼料が与えられているのです。実際、ひと昔前と比べれば明らかに馬っぷりは良くなりました。マーケットブリーダーの方々にとっては当然のことで、より良い値段で売るためには必要なことなのです。現実に日本のマーケットをみても、そういう馬たちに高い値が付けられていますから。ただ、偽らざる感触を言わせてもらうのならば、そういう傾向が強くなるのと反比例するように、馬がどんどん弱くなっています」
人間の世界でも食文化の欧米化などにより、体型や骨の強度など様々な変化が生まれてきていることが伝えられている。その現実に「そう、人間と同じなのです」と勢司師は頷く。
「アメリカのセールなどでは、とても1歳馬とは思えないような馬っぷりの馬たちが多く見られます。そこには徹底的な飼養管理がなされるなど、より高く売るための馬づくりというものがあるのです。それがいまでは、日本、そして馬は自然であるべきという考え方が支配していたヨーロッパのセールでも、馬をつくり始めているのが現実なのです」
では、具体的にどのような変化が問題なのだろうか。勢司師は、その答えを“肥満”だと言う。
「骨の強さをはじめ、全体的に弱くなっているのですが、“太りすぎ”に原因があると思います。人間でも問題になっていますが、幼い頃から栄養価の高い飼料を口にすることによって肉付きは良くなりますが、そうなればその分馬は動かなくなりますから。つまりは飼養管理されることで運動不足に陥りやすいということなのです」
勢司師をはじめ多くのトレーナーたちが感じている「馬が弱くなった」という感触は、アスリートであるべき競走馬が、一方では高い値が付けられる“高価な商品”というもうひとつの側面が生み出していることなのだ。
続く
船橋競馬場の厩務員を経て単身アイルランドへ競馬留学。名馬ニジンスキーを手掛けるヴィンセント・オブライエン厩舎で2年間の修行を積み、日本へ帰国後は昭和61年から美浦・稗田敏男厩舎、平成2年から美浦・国枝栄厩舎で調教助手を経験。平成11年から美浦トレーニングセンターの調教師となる。02年スマイルトゥモローでオークスを制し、GI初勝利を挙げた若手調教師。
★有力馬が続々登場のジャパンC特集はこちら!!★