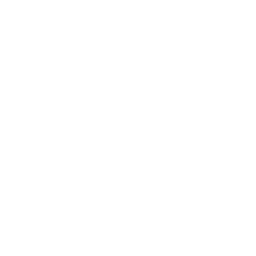第65回有馬記念(27日、中山)は、牝馬5頭がエントリー。グレード制導入の1984年以降、牡牝混合G1で牝馬が年間8勝を挙げたのは今年が初めて。ジャパンCで上位を占めた“3強”トレーナーが、連載「牝馬の時代」で牝馬の活躍についてひもとく。第1回は、有馬記念にカレンブーケドールを送り出すアーモンドアイの国枝栄調教師(65)=美浦=。
史上最多となる芝G1・9勝の偉業を達成したアーモンドアイを手がけた国枝調教師は、まさしく牝馬の時代の到来を感じているトレーナーだ。アーモンドアイの3歳時には、牡馬相手のシンザン記念での重賞初制覇をはじめ、ジャパンCや天皇賞・秋など並みいる牡馬を圧倒してきた。
「牝馬が以前と比べて、アクティブに男馬に挑戦するようになってきた。(牡牝の斤量差は)2キロと決めているけど、大量のデータを集めて科学的に理にかなっているのか、調べてもいい気がする」と、力差が縮まっているとみている。
厩舎を開業した90年頃は、ダイイチルビーやニシノフラワーといった牝馬が安田記念やスプリンターズSを勝つなど、牝馬特有の切れ味の生きるマイル以下では活躍が目立った。しかし芝の中距離以上のG1では、今ほど牝馬の挑戦は多くなかった。
「昔は男馬に比べて、ちょっと能力的に落ちると思われていたけど、ウオッカやダイワスカーレットあたりから変わってきたよね」と、現在につながっていくターニングポイントを挙げる。
また長距離が王道とされてきた競走体系が、カテゴリー別に整備されてきた点も指摘する。牝馬クラシックの3冠目が、11月に行われるエリザベス女王杯から、96年に創設された10月の秋華賞に代わり、3歳牝馬が斤量53キロでジャパンCに挑めるローテが最近では定着している。第1回秋華賞を制したファビラスラフインは、その年のジャパンCで2着に好走。今年の有馬記念に指揮官が送り込むカレンブーケドールも、3歳だった昨年2着と健闘していた。
「牝馬だとフケ(発情)がくるとか、ピークの時期が短いとか言われていたが、馬格がしっかりした馬も増えているからね。我々も普通は桜花賞、オークスと考えるけど、これからはどんどん男馬に挑戦していくことになるかもしれない」と国枝師。トップレベルなら牡馬顔負けの実力を誇り、むしろ強みにさえなってきている。(坂本 達洋)
史上最多となる芝G1・9勝の偉業を達成したアーモンドアイを手がけた国枝調教師は、まさしく牝馬の時代の到来を感じているトレーナーだ。アーモンドアイの3歳時には、牡馬相手のシンザン記念での重賞初制覇をはじめ、ジャパンCや天皇賞・秋など並みいる牡馬を圧倒してきた。
「牝馬が以前と比べて、アクティブに男馬に挑戦するようになってきた。(牡牝の斤量差は)2キロと決めているけど、大量のデータを集めて科学的に理にかなっているのか、調べてもいい気がする」と、力差が縮まっているとみている。
厩舎を開業した90年頃は、ダイイチルビーやニシノフラワーといった牝馬が安田記念やスプリンターズSを勝つなど、牝馬特有の切れ味の生きるマイル以下では活躍が目立った。しかし芝の中距離以上のG1では、今ほど牝馬の挑戦は多くなかった。
「昔は男馬に比べて、ちょっと能力的に落ちると思われていたけど、ウオッカやダイワスカーレットあたりから変わってきたよね」と、現在につながっていくターニングポイントを挙げる。
また長距離が王道とされてきた競走体系が、カテゴリー別に整備されてきた点も指摘する。牝馬クラシックの3冠目が、11月に行われるエリザベス女王杯から、96年に創設された10月の秋華賞に代わり、3歳牝馬が斤量53キロでジャパンCに挑めるローテが最近では定着している。第1回秋華賞を制したファビラスラフインは、その年のジャパンCで2着に好走。今年の有馬記念に指揮官が送り込むカレンブーケドールも、3歳だった昨年2着と健闘していた。
「牝馬だとフケ(発情)がくるとか、ピークの時期が短いとか言われていたが、馬格がしっかりした馬も増えているからね。我々も普通は桜花賞、オークスと考えるけど、これからはどんどん男馬に挑戦していくことになるかもしれない」と国枝師。トップレベルなら牡馬顔負けの実力を誇り、むしろ強みにさえなってきている。(坂本 達洋)