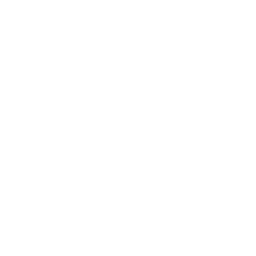競走馬を引退した馬がどうなっていくのか、だが…。
日本でのサラブレッドの生産は1992年に10000頭を超えてピークをむかえたが、その後は減少傾向となったが、2012年に下げ止まりをみせて再び上昇傾向にある。
毎年約7000頭も競走馬を目指すサラブレッドが生まれ、うち、JRAに競走馬登録される馬は毎年5000頭弱である。しかし、3歳のうちに一定の成績が収められない馬はその後JRAに所属していても出走できるレースがなくなる。地方競馬(以下、NARと略)に転厩して既定の勝ち星をあげてJRAに戻るか、別の道を行くか、しかない。
競走馬を引退した馬たちは次世代に血を繋ぐために繁殖に上がるか、乗馬になるか、などの道があるが、毎年これだけの頭数が生まれているのだから、全ての馬で繁殖や乗馬といった"生きたかたちでの経済活動"を継続していくのは不可能だ。
中には動物の餌になる馬もいるが、そういった元競走馬たちはいったん"乗馬"などの違う名目で引退し、その道をたどる。
次に具体的に筆者がしていることを書いておく。筆者はツルマルツヨシという競走馬を引き取り、ツヨシが死ぬまで元気に過ごしてもらおう、という主旨である「ツルマルツヨシの会」の立ち上げと運営の手伝いをしている。
ツルマルツヨシの競走馬時代の担当厩務員をしていた中西氏から「どうしたらツヨシを死ぬまでサポートできるだろうか」と相談を受け、NPO法人である引退馬協会を紹介。その後、会の運営のお手伝いをしながら、現在に至る。
会員の皆さんとのやり取りはすべて中西氏が自らやっており、立ち上げ資金から呼びかけ、とりまとめ、何かトラブルが起きたときの対処などを一手に引き受けている。
中西氏はすでにJRAの厩務員は定年退職しているが、その後は「少しでも自分のできる範囲で自分の経験が役に立てば」と、いくつかの元競走馬の養老牧場を手伝ったりしている。
正直なところ、元競走馬の行く末についての問題は競馬という経済活動の中でダークなテーマとして扱われてきた。ただ、JRAという巨大な組織のもとで、馬券の対象となって走ってきた本来主役であるはずの競走馬たちが華々しい生活をおくったあと、次の用途がないという理由で"処分"されるしかない、というのも心が痛む。
認定NPO法人引退馬協会、引退馬ファンクラブTCC
日本でのサラブレッドの生産は1992年に10000頭を超えてピークをむかえたが、その後は減少傾向となったが、2012年に下げ止まりをみせて再び上昇傾向にある。
毎年約7000頭も競走馬を目指すサラブレッドが生まれ、うち、JRAに競走馬登録される馬は毎年5000頭弱である。しかし、3歳のうちに一定の成績が収められない馬はその後JRAに所属していても出走できるレースがなくなる。地方競馬(以下、NARと略)に転厩して既定の勝ち星をあげてJRAに戻るか、別の道を行くか、しかない。
競走馬を引退した馬たちは次世代に血を繋ぐために繁殖に上がるか、乗馬になるか、などの道があるが、毎年これだけの頭数が生まれているのだから、全ての馬で繁殖や乗馬といった"生きたかたちでの経済活動"を継続していくのは不可能だ。
中には動物の餌になる馬もいるが、そういった元競走馬たちはいったん"乗馬"などの違う名目で引退し、その道をたどる。
次に具体的に筆者がしていることを書いておく。筆者はツルマルツヨシという競走馬を引き取り、ツヨシが死ぬまで元気に過ごしてもらおう、という主旨である「ツルマルツヨシの会」の立ち上げと運営の手伝いをしている。
ツルマルツヨシの競走馬時代の担当厩務員をしていた中西氏から「どうしたらツヨシを死ぬまでサポートできるだろうか」と相談を受け、NPO法人である引退馬協会を紹介。その後、会の運営のお手伝いをしながら、現在に至る。
会員の皆さんとのやり取りはすべて中西氏が自らやっており、立ち上げ資金から呼びかけ、とりまとめ、何かトラブルが起きたときの対処などを一手に引き受けている。
中西氏はすでにJRAの厩務員は定年退職しているが、その後は「少しでも自分のできる範囲で自分の経験が役に立てば」と、いくつかの元競走馬の養老牧場を手伝ったりしている。
正直なところ、元競走馬の行く末についての問題は競馬という経済活動の中でダークなテーマとして扱われてきた。ただ、JRAという巨大な組織のもとで、馬券の対象となって走ってきた本来主役であるはずの競走馬たちが華々しい生活をおくったあと、次の用途がないという理由で"処分"されるしかない、というのも心が痛む。
認定NPO法人引退馬協会、引退馬ファンクラブTCC
みんなのコメント(2件)
-

日冠はいい加減ここの自治するのやめたらw
お前になんの力もない。
今回の部分削除は要約として十分成立してるし、気に食わないからっていちいち噛みつくの見てて気持ち悪い。 -

善意を利用する人もいるので、十分に調べて行う事。
筆者が特に主張したい部分は何で外して投稿するんですか?
それに先日コメントしたニュースというのも投稿してますね。
なら今記事の部分削除引用は極めて悪質。
ここでよく引退馬について出てくるけど、中身を全く理解せず綺麗事でいい話だとし安易に乱発する人が多いが、誤情報の拡散だけでなく不正連中の私腹肥えにも繋がり本末転倒。無責任にも程がある。
どうせ自身の点数稼ぎだけが目的だからそんなのどうでもいいんでしょうがね。