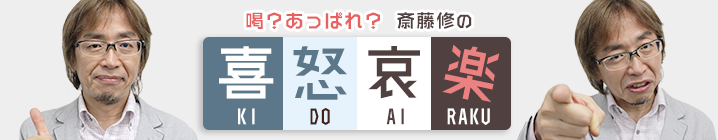
リワードアヴァロンの快挙と高知競馬の今
- 2020年06月16日(火) 18時00分
父も活躍した高知で「ダービー」を勝つ奇跡
6月14日に行われた高知優駿では、ここまで2戦の走りがいまいちだったため人気を落としていたリワードアヴァロンが見事に逃げ切って見せた。
気性的なことなのか、リワードアヴァロンはいつも直線に入ったあたりで頭を上げて馬がブレーキをかけてしまう。普段調教をつけている岡村卓弥騎手がレースで初めて手綱をとった前走は、3コーナー過ぎから頭を上げてしまい、それゆえ勝ち馬から4秒5も離されて8着。高知優駿では永森大智騎手に戻って、好スタートからマイペースの逃げに持ち込んだ。直線を向いたところでやはり頭を上げたがすぐに立て直し、ゴールまでなんとかまじめに走らせて逃げ切った。
リワードアヴァロンといえば、父グランシュヴァリエも現役時代に高知所属として活躍。その産駒が、父と同じ雑賀正光厩舎に所属して世代のトップを争う活躍を見せているため注目されているわけだが、その可能性たるやほとんどゼロに近い確率の出来事といってもいい。
近年、地方出身の種牡馬ではフリオーソが活躍しているが、時代の流れもあってのこと。そもそも地方馬はどんなに活躍しても種牡馬になることすら難しかったし、仮に種牡馬になったとしても配合相手に恵まれず、産駒の活躍もほとんど期待できないというのが常だった。
昭和の終わり頃から競馬を見ているが、高知所属馬が種牡馬になったという例は記憶にない(もしあったら教えて下さい)。
バブルの時期とその後しばらく、地方競馬はどこも好況だった。高知競馬でも高知県知事賞の1着賞金が最高で1200万円という時代があった(95年)。とはいえ、古馬の重賞戦線で活躍したのはほとんどが中央や南関東からの移籍馬。言い方は悪いが、いわば“都落ち”してきた馬たち。
90年代、“新春賞”として正月に実施されていた高知県知事賞の勝ち馬の年齢を見ると、7歳3頭、8歳6頭、9歳1頭。近年の勝ち馬より、ずっと高齢の馬たちだった。遠回しな言い方になるが、それが地方競馬それぞれの役割だった。それゆえ高知から種牡馬に、ということにもならない。
話を戻す。高知所属馬としてはきわめてめずらしく種牡馬となったグランシュヴァリエの初年度産駒(2017年生まれ)は6頭が血統登録されたが、そのうち競走馬としてデビューしたのは4頭。いずれも北海道・堂山芳則厩舎からデビューし、うち2頭はすでに登録を抹消。現役の2頭はともにホッカイドウ競馬のシーズン終了後に雑賀正光厩舎に移籍した。その1頭がリワードアヴァロンで、もう1頭のリワードグランも門別でアタックチャレンジを勝ち、高知でも2勝を挙げている。
こうした出自のわずかな産駒から、父も活躍した高知で、しかも“ダービー”を勝つなど、いかに奇跡的なことだったか、おわかりいただけるだろうか。
そして今年2歳のグランシュヴァリエ産駒は4頭。残念ながらこの世代の種付を最後に“用途変更”となっているので、この4頭が最後の産駒となる。
リワードアヴァロンのことでは雑賀調教師に何度か話をうかがっていたので、高知優駿を勝ったあと、日をあらためてお祝いの電話をしようと思っていたところ、逆に当日の夜に電話をいただいた。よほど嬉しかったに違いない。
高知で世代のチャンピオンになったからには「次はどこか遠征に行きますか?」と聞いたところ、「遠征には行かない。高知で十分稼げるから」と返ってきた。
何気ないやりとりだったが、あらためて雑賀調教師の言葉としては、深いし、重みがある。
今、高知競馬の売り上げが好調なのはさまざまなところで伝えられているが、2008年度には1日平均で4042万円余りにまで売上が落ち込んだ。全国の主催者の中でも抜けて低い金額だった。
その後、高知競馬は通年ナイターの導入などで徐々に持ち直していくのだが、グランシュヴァリエが中央1000万条件から雑賀厩舎に移籍してきたのは2009年の終盤。初戦となったのは年明けで、いきなり川崎の報知オールスターCに出走し、8番人気というまったくの低評価ながら、マズルブラストに半馬身差2着と好走して驚かされた。
そこからグランシュヴァリエの全国行脚が始まった。その2010年のマイルチャンピオンシップ南部杯では3着、翌2011年にはJBCクラシック(大井)で4着。勝利には至らなかったものの、中央の一線級相手にダートグレードでも何度か好走を見せた。
重賞初勝利は2012年3月、福山のファイナルグランプリ。地元高知の重賞は同年大晦日の高知県知事賞が初勝利だった。地元の重賞を使っていれば、もっと勝てたに違いないが、なぜ強敵相手でも遠征を続けたかといえば、高知の賞金が安すぎたからということにほかならない。
もっとも落ち込んだ2008年の最下級条件の1着賞金は9万円。重賞でも、最高賞金の高知県知事賞が135万円で、もっとも高かった時代の約1/9。そのほかの古馬重賞は50万円、高知優駿はわずか27万円だった。
それゆえ賞金を稼ぐには他地区遠征に活路を求めるしかなく、雑賀厩舎だけでなく、いくつもの有力厩舎が積極的に他地区に出ていった。
いまでも不思議なのは、なぜそれほど賞金が低い時代の高知に、グランシュヴァリエをはじめとして、他地区に遠征して通用するほどの能力の馬がいたのか。この頃の高知所属馬は、他地区遠征であっと言わせることがたびたびだった。
高知優駿の1着賞金は、地方競馬のダービーシリーズに組み込まれた2017年に、前年の100万円から500万円に一気にアップ。さらに今年は700万円になった。
2019年度の高知競馬の1日平均の売上5億1754万円余りは、ついに兵庫を超え、地方競馬では南関東4場に次ぐ5番目となった。無観客開催となったこの3月の1日平均は6億4千万円余り、4月は南関東のナイターと競合して例年であれば下がるのだが、今年はなんと6億7千万円余りで、3月をさらに上回った。
今回の高知優駿では、高知優駿1レースの売上が2億7106万6200円で、当日1日では9億円超。
グランシュヴァリエに代表される、高知競馬どん底の時代を支えた馬と人がいてこそ、今の高知競馬がある。
1964年生まれ。グリーンチャンネル『地・中・海ケイバモード』解説。NAR公式サイト『ウェブハロン』、『優駿』、『週刊競馬ブック』等で記事を執筆。ドバイ、ブリーダーズC、シンガポール、香港などの国際レースにも毎年足を運ぶ。









