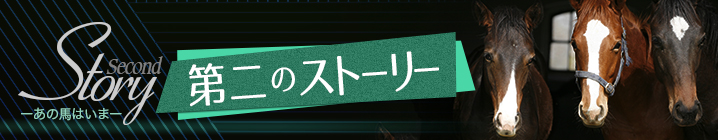
「寄り添い、命を看取り、送り出す」養老牧場の大きな仕事 高知・あしずりダディー牧場(7)
- 2020年07月07日(火) 18時00分

現役引退後はウルルという名前で過ごしていたナムライナズマ(提供:あしずりダディー牧場)
最後は、まるで駈歩をするように…
ナムライナズマもあしずりダディー牧場で晩年を過ごした1頭だった。
ナムライナズマは、1993年4月12日、北海道浦河町の毛内孫一さんの牧場で生まれた。父タマモクロス、母チャリスオブシルバー、母の父がGraustarkという血統で、半妹に2001年の京都牝馬S(GIII)を制したグレイスナムラがいる。
ナムライナズマ自身は重賞勝ちこそないものの、ダンスインザダークやフサイチコンコルド、イシノサンデーが活躍した1996年のクラシック戦線を彩った1頭だ。栗東の目野哲也厩舎から1995年8月13日に函館でデビューし、9月10日に3戦目で未勝利を脱出。10月7日には、オープンのもみじSで2勝目を挙げ、明け4歳(現3歳)になってからは、きさらぎ賞(GIII)で4着、毎日杯(GIII)でのちのNHKマイルC優勝のタイキフォーチュンの2着と健闘して、皐月賞(GI・10着)にも出走した。秋シーズンは神戸新聞杯(GII・6着)、京都大賞典(GII・12着)とステップレースから本番の菊花賞(GI)に駒を進めた。しかし、戦前に逃げ宣言をしながらも出遅れてしまい、見せ場を作れぬまま17着と殿負けを喫し、結果的にこれがナムライナズマの最後のレースとなった。
競走馬生活にピリオドを打ったナムライナズマは、ウルルという馬名で乗馬として第二の馬生を歩んできた。やがてそのお役目を終えたウルルは、この連載5回目で紹介したアパルーサのアルファーをあしずりダディー牧場から買い上げて、愛馬を亡くしたばかりの女性にプレゼントしたという人(ダディー牧場に馬を預託する馬主でもある)と、セニョールベストの馬主が預託料を折半する形を取った。
「お二人はウルルが亡くなるまで、大切にしてくれました」(宮崎栄美さん)
優しい性格のウルルは、ダディー牧場で穏やかな日々を過ごしていたが、その体には病魔が忍び寄っていたのだった。
「はじめはテディベアのように巻き毛になって、冗談半分で可愛いねとか言っていたんですよ。それが夏になっても毛が抜けずに、ボーボーになっていました。そうこうしているうちにフレグモーネのように脚が腫れてきたりと、様々な病状が現れてくるようになったんです」
診断はクッシング症候群だった。ホルモンの異常により引き起こされる難病だ。
「最後は口があかなくなって、目のあたりは溶けてきていました」
これ以上、生かしておくと苦しませるだけということで、安楽死の処置を取ることに決めた。立つこともやっとの状態ではあったが、宮崎さんは安楽死の前にせめて放牧をしてやりたいと考え、ウルルを外に出した。

穏やかで優しい瞳のウルルは性格も優しいという(提供:あしずりダディー牧場)
「ヨタヨタと出てきて崩れ落ちるように砂の上に倒れました。それから2度と立ち上がることができなかったので、このまま楽にしてあげた方がいいと思いました」
獣医は高知競馬での仕事をこなして、ダディー牧場に到着した時は24時を回っていた。空を見上げるとそれは美しい満天の星空が広がっていた。
「星空の下、ウルルを抱きかかえながら、歌を歌いました。そして最後にウルルと呼びかけて、いっぱい走って天国に行くんだよ、走る時にはちゃんと合図してねと伝えて、獣医さんに注射を打ってもらいました。すると脚をパッ、パッ、パッとまるで駈歩をするような感じの動きをしたんです」
脚の動きは止まり、ウルルの心臓も止まった。
「獣医さんが女性ということもあって、最後は2人で泣きました。栃栗毛という変わった栗毛で、体は大きくて立派でしたけど、本当に優しくて可愛らしい馬でした。忘れることはできないですね」
2019年3月5日、ウルルことナムライナズマは満天の星空に駈け上がっていった。満26歳の誕生日の約1か月前のことだった。

牧場にはウルルを偲んで“ウルルの木”が植えられている(提供:あしずりダディー牧場)
宮崎さんの取材を通して、養老牧場というのは馬たちの最後を看取るのが大きな仕事の1つなのだと再認識させられた。どんなに気をつけていても、病や事故は起こる。それで天寿を全うできずに命を終える馬もいれば、年老いて老衰に近い形で天に召される馬もいる。生産牧場、育成牧場、トレセンを含む競馬場、乗馬クラブなどでも亡くなる馬はいるので、養老牧場だけが大変だというつもりはない。だが養老牧場で過ごす馬たちはその場所で最後を迎えることがほぼ確実だ。つまり入厩してきた馬すべての最後を看取らなければならないということだ。
目の前の命が失われたことが悲しいというだけではない。例えば重い疝痛で苦しむ馬の看護、脚腰が弱り起き上がれなくなった馬を立たせる作業の困難さ、それでも立てなくなってしまった馬を安楽死にするかどうかの決断を迫られる。いざ安楽死の処置をする時にも1番近くに寄り添う。高齢の馬の場合、朝、馬房に行ってみると、あるいは放牧地で亡くなっていたということもあるようで、それもまた発見した時のショックが大きいのではないかと想像する。養老牧場という響きは、のんびり穏やかな感じを受けるが、1頭1頭の命を看取り、送り出すという仕事をする側は、精神的にも肉体的にもかなりきついに違いない。だが競走馬や乗馬として頑張ってきた馬たちの余生をより良いものにしたいという志のもと、全国各地に養老牧場を営んでいる人々が存在しているのも事実だ。
牧場を開場以来、宮崎さんも何頭もの馬たちを見送り、そのたびに深い悲しみを味わってきた。それでもなお宮崎さんは歩みは止めず「まだ道半ば」と話す。馬たちのために、ダディー牧場はさらに進化しようとしていた。
(つづく)
▽ NPO法人 あしずりダディー牧場 命の会 HP
http://www.horsetrust-ashizuri.com/
▽ NPO法人 あしずりダディー牧場 命の会 Facebook
https://www.facebook.com/daddyranch/
北海道旭川市出身。少女マンガ「ロリィの青春」で乗馬に憧れ、テンポイント骨折のニュースを偶然目にして競馬の世界に引き込まれる。大学卒業後、流転の末に1998年優駿エッセイ賞で次席に入賞。これを機にライター業に転身。以来スポーツ紙、競馬雑誌、クラブ法人会報誌等で執筆。netkeiba.comでは、美浦トレセンニュース等を担当。念願叶って以前から関心があった引退馬の余生について、当コラムで連載中。












