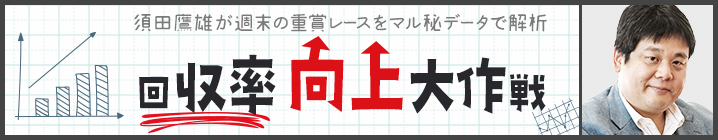
1400mというビミョーさ
- 2011年02月21日(月) 00時00分
今週は1400mの阪急杯が行われる。
1400mという距離は、解釈によってどうともとれる距離である。1200mの馬にもう1ハロン頑張ってもらおうという風にも考えられるし、1600mの馬にちょっとスピード面で頑張ってもらおうとも考えられる。
もうひとつ、競馬場ごとに同じ1400mでもニュアンスの違いは無いのかという問題もある。コース形態や坂の有無などで、必要とされる能力が違うかもしれない。
まず、1400mの古馬重賞全体について考えてみよう。東京や阪神の改修前も含め、芝1400mの古馬重賞は2001年以降計35レース行われている。
そこに出走した馬たちの前走距離別成績を見ると、勝率・連対率では1600m組←1200m組となっている。ほかならぬ前走1400m組の成績はもっと悪いので、スタミナ云々よりは番組構成の影響だと思うが、どちらかということだと1600mタイプのほうが安心感はあると言える。
続いて、各場別の違いだ。サンプル数を増やすため、古馬のオープン特別・重賞というくくりで東京(2003年以降)、阪神(2006年)、京都(2001年以降)の優勝馬をピックアップし、当該レース以前の平均優勝距離・平均連対距離を導いてみよう。結果はこのようになる。
※競馬場、平均優勝距離、平均連対距離の順。
東京 1493.5m 1505.7m
阪神 1464.7m 1476.1m
京都 1431.0m 1438.5m
対象頭数が最も多い東京でも22頭、京都はほぼスワンSのみで11頭だからどの程度意味があるのかは微妙だが、東京はスタミナが必要っぽいというイメージには合致するし、スプリンターが強いイメージのあるスワンSにも納得がいく。
ただ、3場とも1400mを超える数値に落ち着いているわけで、やはり生粋の1200mタイプというよりはマイルも視野に入るタイプのほうがよいのかもしれない。
1400mという距離は、解釈によってどうともとれる距離である。1200mの馬にもう1ハロン頑張ってもらおうという風にも考えられるし、1600mの馬にちょっとスピード面で頑張ってもらおうとも考えられる。
もうひとつ、競馬場ごとに同じ1400mでもニュアンスの違いは無いのかという問題もある。コース形態や坂の有無などで、必要とされる能力が違うかもしれない。
まず、1400mの古馬重賞全体について考えてみよう。東京や阪神の改修前も含め、芝1400mの古馬重賞は2001年以降計35レース行われている。
そこに出走した馬たちの前走距離別成績を見ると、勝率・連対率では1600m組←1200m組となっている。ほかならぬ前走1400m組の成績はもっと悪いので、スタミナ云々よりは番組構成の影響だと思うが、どちらかということだと1600mタイプのほうが安心感はあると言える。
続いて、各場別の違いだ。サンプル数を増やすため、古馬のオープン特別・重賞というくくりで東京(2003年以降)、阪神(2006年)、京都(2001年以降)の優勝馬をピックアップし、当該レース以前の平均優勝距離・平均連対距離を導いてみよう。結果はこのようになる。
※競馬場、平均優勝距離、平均連対距離の順。
東京 1493.5m 1505.7m
阪神 1464.7m 1476.1m
京都 1431.0m 1438.5m
対象頭数が最も多い東京でも22頭、京都はほぼスワンSのみで11頭だからどの程度意味があるのかは微妙だが、東京はスタミナが必要っぽいというイメージには合致するし、スプリンターが強いイメージのあるスワンSにも納得がいく。
ただ、3場とも1400mを超える数値に落ち着いているわけで、やはり生粋の1200mタイプというよりはマイルも視野に入るタイプのほうがよいのかもしれない。
1970年東京生まれ。競馬評論家、ギャンブル評論家。中学生時代にミスターシービーをきっかけとして競馬に興味を持ち、1990年・大学在学中に「競馬ダントツ読本」(宝島社)でライターとしてデビュー。以来、競馬やギャンブルに関する著述を各種媒体で行うほか、テレビ・ラジオ・イベントの構成・出演も手掛ける。競馬予想に期待値という概念を持ち込み回収率こそが大切という考え方を早くより提唱したほか、ペーバーオーナーゲーム(POG)の専門書をはじめて執筆・プロデュースし、ブームの先駆けとなった。



