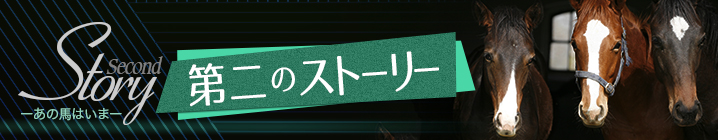
引退馬を預けたい人と預かる人をつなげるサイト「引退馬預託施設INFO」がオープン!
- 2019年10月08日(火) 18時00分

▲引退馬預託施設INFOより
引退馬を引き取りたい…けど、どうすれば?
競馬ファンなら大好きだった馬が引退後にどのような道を辿るのか、乗馬愛好者なら日頃よく乗っている練習馬がその役目を終えた後にどこへ行ってしまうのか、気になっている方が多いのではないだろうか。
自分が好きだった競走馬やレッスンでよく騎乗した練習馬を競馬や乗馬から引退した後に引き取って、養老牧場等に預託している人も実際に存在するし、これまでもそのような人馬を取材して当コラムで紹介をしてきた。
だが引き取るにはどう動けば良いのか、いったいどのくらい経費がかかるのか、どこに預ければ良いのかがわからないという方がほとんどというのが実情だ。
その悩みの1つを解消してくれるサイトが、このたび認定NPO法人引退馬協会のホームページ内にオープンした。その名も「引退馬預託施設INFO」。引退馬を引き取って余生を支えたいと考えている方々に向けて、北は北海道、南は九州までの引退馬の繋養施設の情報を集めて発信している。
「引退馬の預託施設を探すのに、皆さん苦労をしていらっしゃるというのを目の当たりにすることが多かったんですね。例えば預託料などの金額面や、どのくらいの広さがあるのかなど聞きづらいことがありますよね。それでよく確認せずに預託先を決めてあとからトラブルになったりもしていましたので、物件の情報が記載されている不動産屋さんの張り紙のようなものがあればいいのではないかと思いました」
と話すのは、認定NPO法人引退馬協会の代表理事の沼田恭子さんだ。
「預託施設に関する情報があれば、引退した馬を自分がどうしていきたいのかを具体的に考えることができるのではないかと思います。事前に情報を収集して、自分で探すことができますし、気になった施設に足を運んで見学して検討することもできます。自らの目で確かめて預託先を決めてほしいですね」(沼田さん)
預ける側と受け入れる側の需要と供給は必ずしも一致しないものだ。このサイトで紹介されているから大丈夫と預託先を決めるのではなく、やはり自分や愛馬に合った施設はどこなのかを自らしっかり確認をし、よく考えて決めることがポイントとなるだろう。
サイトが立ち上がったのは今年の9月25日だが、2018年秋からセカンドライフやサードライフを終えた馬たちが余生を送るための繋養施設の実態調査を実施している。今年1月に横浜赤レンガ倉庫で開催されたホースメッセの引退馬協会のブースには、その時点で集まっていた引退馬預託施設の情報が、不動産会社に張られている物件情報に似た形で掲示された。ホースメッセは競馬というより、むしろ乗馬関係者、愛好者向けのイベントでもある。
「乗馬クラブの練習馬をゆくゆくは引き取りたいがどうすれば良いのかわからないという人が、具体的に引き取りについて考えるきっかけになってくれればというのもありました」(沼田さん)
と、ホースメッセで情報を掲示した狙いを教えてくれた。
10月8日現在、サイトには28施設が紹介されているのだが、そこには住所やアクセス方法、電話番号等の連絡先をはじめ、代表者名、WEBサイトやSNSアドレス、メールアドレス、現在繋養している養老馬頭数、受け入れ可能な養老馬頭数、募集馬の条件(例:養老馬・休養馬・牝馬・セン馬等)、預託料(月額)、施設(例:厩舎・放牧地・洗い場等)、馬体ケア連携等(例:獣医師・装蹄師)という項目が設けられており、最後に各牧場、乗馬クラブの特徴が記載されている。
私自身、実際に馬を引き取るにあたって預託先を探すのに時間がかかり、しかもいざクラブの人と会話をする段階になると、何を確認したり質問をすれば良いのかがわからなくなって、肝心なことを聞き忘れるという失敗もした。また、馬を預託してしまうと、不満や疑問が出てきてもなかなか言い出しづらいものだ。
だがこのサイトで紹介されている各施設について、これだけ詳細に情報が公開されていると、どのような施設なのかをイメージしやすい。例えば自分はいくらまでなら預託料を払い続けられるのか、通いやすい場所が良いのか、会うのは年に数回でも良いから広い放牧地のある北海道の牧場が良いのかなど、自分の希望や愛馬に合った場所も見つけやすくなりそうだ。
また今回掲載されている養老馬を繋養する牧場や乗馬クラブは、自薦他薦のほか、引退馬協会サイドで関係している牧場や乗馬クラブなどに趣旨を説明して、情報を提供してもらっているという。
「養老馬を何頭受け入れることができるのかなど、預かる側の受け入れ条件がはっきりしていないケースもありましたので、今回の掲載をきっかけに預かる牧場やクラブ側も具体的に条件や数字を考えるきっかけになったと思います」(沼田さん)
ホームページを開設したり、SNSで養老預託馬募集の情報発信をしている牧場等も見受けられるが、中にはホームページやSNS、メールアドレスを持っていない場所もあるので、今回の引退馬預託施設INFOのようなサイトはそのような施設の味方にもなりそうだ。
JRAが引退馬支援を始めたことにより、引退した馬たちを繋養する施設は今以上に必要になってくるだろう。個人で引き取りたい人や、1頭を複数人数で面倒をみたいというグループも増えていく可能性もありそうだ。それを考慮しても「引退馬預託施設INFO」のような引退馬の受け入れ施設の情報は時代にマッチしていると言えよう。
なお「引退馬預託施設INFO」では、現在も自薦他薦問わず、繋養施設の情報を募っている。
(つづく)
認定NPO法人引退馬協会
https://rha.or.jp/index.html
引退馬預託施設INFO
https://rha.or.jp/yotaku_info/index.html
- 1 / 10
- 次のページへ
北海道旭川市出身。少女マンガ「ロリィの青春」で乗馬に憧れ、テンポイント骨折のニュースを偶然目にして競馬の世界に引き込まれる。大学卒業後、流転の末に1998年優駿エッセイ賞で次席に入賞。これを機にライター業に転身。以来スポーツ紙、競馬雑誌、クラブ法人会報誌等で執筆。netkeiba.comでは、美浦トレセンニュース等を担当。念願叶って以前から関心があった引退馬の余生について、当コラムで連載中。













