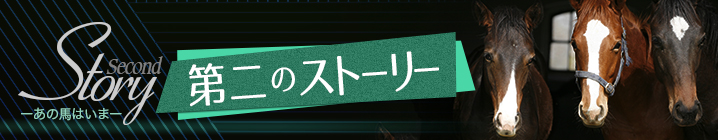
星になったキョウエイボーガン(3)「最後は目で合図して…」元旦、静かに天国へ
- 2022年02月22日(火) 18時00分

もぐもぐ…リンゴをたべるキョウエイボーガン(撮影:朝内大助)
この馬は自分の子供と同じだから…
適度な運動を行い、手厚いケアを受け、会員やファンからの愛情をたくさん受けて、ボーガンは晩年を過ごしてきた。こうして2021年も無事に年を越せるかと思った矢先、異変が起きた。持病の蹄葉炎が悪化したのだ。
「暮れあたりからボーガンが横になって寝なくなりました。28日に1回横になったのですけど、起き上がれなくなりました。それで僕が手を貸したら何とか起き上がれたんです。その後厩(うまや)で少しずつ歩いてはいたのですが、横になって寝なかったんです。なので今度寝たらダメかなと思っていました」(乗馬クラブアリサ・中山光右さん)
31日、大晦日にボーガンは力尽きたのか、ついに横たわった。だが苦しそうにはしていない。
「リンゴや人参を持っていったら食べるんです」
食欲はまだ残っていたが、介助をしても立ち上がらせるのは難しい状況になった。
「痛みが出てきたり、起き上がろうとして立てずにバタバタして怪我を負うこともありますから」
中山さんはボーガンを必要以上に苦しませたくはないと考え、獣医師と相談した。
「その際に、この馬は自分の子供と同じだし、辛いのを見たくない。だから楽にしてあげてほしいと伝えました」
ボーガンが静かに天国へと旅立ったのは、2022年1月1日。元日の朝だった。

ボーガンは今年の元旦、静かに天国へ(撮影:朝内大助)
中山さんは、キョウエイボーガンの生産者の弟に連絡を入れた。
「生産した方は既に亡くなられているのですけど、その弟さんが以前会いに来てくださってね。このように大事にしていただいてありがとうございますと喜んでいらっしゃいました。何かあったら知らせてくださいと言われていたので、電話をかけました」
「取材で会いに来てくれましたし、伝えておかなきゃと思って」と、育成時代のボーガンに跨った経験があり、6年前の当コラムでの取材時に一緒に牧場を訪れた小島茂之調教師にも連絡を入れた。
電話で中山さんの取材をしたのは、ボーガンが亡くなって1か月少したった2月5日だった。
「寂しくなりましたよ。これで長く一緒にいるのは、ルージュだけになりました」
中山さんの張りのある声が、少しくぐもった。
「ボーガンは頭が良いんだよね。放牧していてもどの馬についたら得かというのがわかっていましたから。アリサ(乗馬クラブ名の由来にもなっていて、女ボスとして君臨していた)が生きている頃、その馬に必ずボーガンはくっついていました。アリサというのがすごい気性の馬で、怪我をしても治療したり、薬をつけたことがないというか、つけられないんです(笑)。だから怪我をした時にはバケツに消毒液を入れて、離れた位置からボーンとかけていました(笑)。そんなの自分でなめて治すわみたいな感じの馬でしたからね。
いつもボーガンとルージュはアリサの横にピッタリくっついて歩いていましたよ。今、渡辺はるみさん(浦河の養老牧場の渡辺牧場)のところに帰したラック(キゼンラック)という馬は、アリサが嫌いだから1番離れたところにいました。放牧中の馬模様がとても面白かったですよ」
ボーガンは人も大好きだった。
「会員さんなど誰かが会いにくれば、厩(うまや)の中に入ってブラシをかけてもらったり。大人しいですからね。元気だったのは20歳くらいまでかな。ただ性格そのものは穏やかでしたから。ブラッシングしてもらうと喜んでいましたよ。目がトローンとしてね」
次々とボーガンの思い出話が、中山さんの口から語られた。
「いまだに花が届くんですよ。厩(うまや)に入り切らないくらい、花がいっぱい。すごいですよね。ビックリしました。それだけボーガンを思う人がたくさんいて、あの馬は幸せだろうね」

たくさんの人の思いが詰まったボーガンの厩(提供:引退馬協会)
現役時代はヒール役だったボーガンの晩年は、多くの人の愛に包まれていた。
「僕なんかそれこそ何十頭もこれまで見送ってきましたから。それでも、全然慣れないです。ましてやボーガンのように20年以上の付き合いとなると、まるっきり自分の身内ですよ。あいつも僕の言いたいことがわかるだろうし、僕も同じ。お互いに言いたいことがわかっているから。最後は目で合図する。そんな感じでした」
何十頭の馬の命を見送ってきても慣れない。その言葉は重い。それでも馬との信頼関係を築きながら、その命を繋いできた。
屠場に行くはずだったボーガンをファンの女性が引き取り、中山さんご夫妻の運営する乗馬クラブアリサで過ごした。女性から引退馬協会に引き継がれた後も、棲家は変わらずアリサでの穏やかな毎日だった。「幸せ」という言葉を安易に使わないようにはしているのだが、キョウエイボーガンには「幸せ」がよく似合う。取材を終えてそう感じていた。
(了)
北海道旭川市出身。少女マンガ「ロリィの青春」で乗馬に憧れ、テンポイント骨折のニュースを偶然目にして競馬の世界に引き込まれる。大学卒業後、流転の末に1998年優駿エッセイ賞で次席に入賞。これを機にライター業に転身。以来スポーツ紙、競馬雑誌、クラブ法人会報誌等で執筆。netkeiba.comでは、美浦トレセンニュース等を担当。念願叶って以前から関心があった引退馬の余生について、当コラムで連載中。













