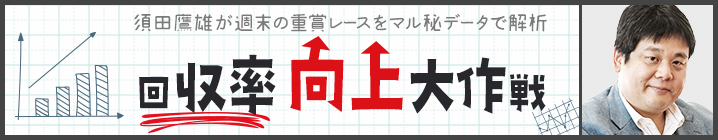
【宝塚記念予想】「意外な馬の上がり最速」はあるか
- 2023年06月20日(火) 12時00分
少ない手がかりから探し出す候補
宝塚記念は上がり最速が無駄にならないレース、という話を本欄に書いたのは2019年のことだったと思う。実際、宝塚記念では後方からそこそこの着順まで伸びただけの上がり最速というものがほとんどなく、上がり最速を取ったが4着以下というケースは2004年のツルマルボーイ(6着)が最後。その後の上がり最速馬はすべて連対している。
厄介なのは、どの馬が上がり最速になるか、他のレースより分かりづらいということだ。15年のデニムアンドルビー、18年ワーザーのように4角後方から伸びてきた「いかにも」というケースはあるが、先述した19年リスグラシューは通過順が2-2-2-2、21年クロノジェネシスは4-4-3-4、昨年のヒシイグアスは17頭立てで6-6-6-5だった。ゴールドシップも好位からの上がり最速を2度取っている。そして、ここに挙がった馬はいずれもレースに出るたび上がり最速というタイプでもない。
宝塚記念は緩むラップが少なく、消耗戦の色彩が強くなることがあり、上がりタイムもかかることが多い(雨が絡んでいることも多いのだが)。東京や、同じ阪神でも外回りの良馬場でキレキレの脚を発揮するのとはまた違うタイプの馬が、上がり最速を獲得し、そのうえで連対する可能性がある。また、それを予想するのが宝塚記念の醍醐味である。
ただ、あまりに手がかりが少ない。上がりタイムは馬場状態にもよるので道中位置を参考にすると、準オープン以上・芝1800m以上・3角5番手以内という条件で上がり最速を取ったことがあるのはダノンザキッド、ジオグリフ、ジェラルディーナ、ジャスティンパレスの4頭。無理やり決め打つならこのあたりが候補になるだろうか。
1970年東京生まれ。競馬評論家、ギャンブル評論家。中学生時代にミスターシービーをきっかけとして競馬に興味を持ち、1990年・大学在学中に「競馬ダントツ読本」(宝島社)でライターとしてデビュー。以来、競馬やギャンブルに関する著述を各種媒体で行うほか、テレビ・ラジオ・イベントの構成・出演も手掛ける。競馬予想に期待値という概念を持ち込み回収率こそが大切という考え方を早くより提唱したほか、ペーバーオーナーゲーム(POG)の専門書をはじめて執筆・プロデュースし、ブームの先駆けとなった。









